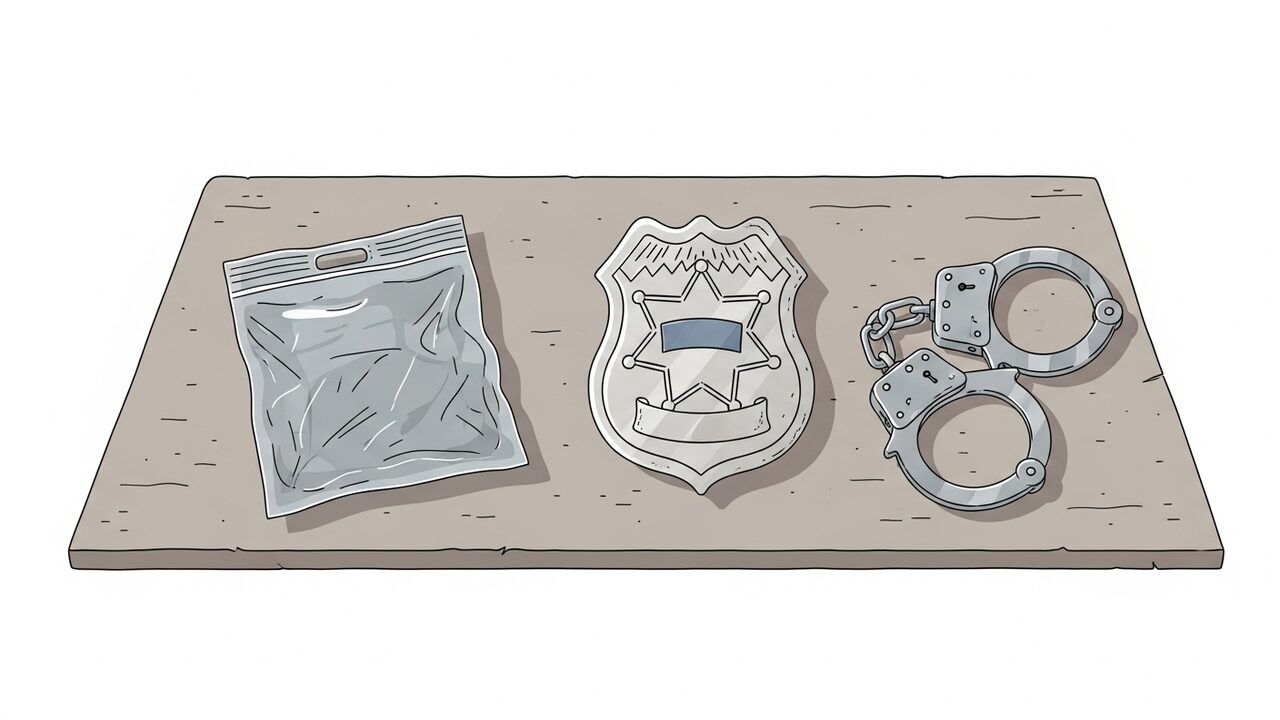休業手当の訴訟リスク|「使用者の責」の解釈と判例、賃金全額請求への備え

企業の経営判断として休業を検討する際、従業員への休業手当の支払義務は避けて通れない法務リスクです。特に、支払い義務の根拠となる「使用者の責に帰すべき事由」の解釈は訴訟の最大の争点となり、その範囲は経営者の想定以上に広い場合があります。この記事では、労働基準法第26条に基づく休業手当の支給要件から、企業側が敗訴する具体的なケースを示す重要判例、そして訴訟を回避するための実務的な予防策までを網羅的に解説します。
休業手当の基本|労働基準法第26条の支給要件
休業手当とは?支給対象者と支払いの法的根拠
休業手当とは、労働基準法第26条に基づき、会社の都合(使用者の責に帰すべき事由)によって労働者を休業させた場合に、会社が支払う義務を負う手当のことです。この制度は、労働者の責によらない休業期間中の最低生活を保障することを目的としています。
本来、労働の対価として賃金が支払われるため、「働かなければ賃金は発生しない」というノーワーク・ノーペイの原則が適用されます。しかし、休業の原因が会社側にある場合にこの原則を貫くと労働者の生活が脅かされるため、例外的に賃金の一部支払いが法律で義務付けられています。
支給対象者は雇用形態を問わず、会社と雇用契約を結んでいるすべての労働者が含まれます。派遣社員の場合は、雇用元である派遣元企業に支払い義務があります。また、採用内定者も、労働契約が成立しているとみなされれば、自宅待機などを命じられた際に支給対象となる可能性があります。一方で、業務委託契約を結ぶ個人事業主やフリーランスは、労働基準法上の労働者に該当しないため原則として対象外です。
- 正社員
- 契約社員、嘱託社員
- パートタイマー、アルバイト
- 派遣社員(支払義務は派遣元)
- 日雇い労働者
- 採用内定者(労働契約成立後)
支給条件①:使用者の責に帰すべき事由による休業であること
休業手当の支給義務が発生する第一の条件は、休業の原因が「使用者の責に帰すべき事由」、つまり会社側の都合や責任にあることです。この事由は非常に広く解釈され、会社に直接的な過失がない場合も含まれます。裁判例では、経営者として不可抗力を主張できないすべてのケースが該当すると考えられています。
具体的には、経営上・管理上の障害に起因する休業は、原則としてすべて「使用者の責に帰すべき事由」と判断されます。
- 原材料の不足や受注の減少による操業停止
- 資金繰りの悪化や経営不振による事業活動の縮小
- 機械の故障やメンテナンスによる生産ラインの停止
- 親会社の経営不振の影響による下請工場の休業
- 監督官庁からの行政指導や勧告に基づく操業停止
- 法的強制力のない行政からの休業要請に応じた自主的休業
支給条件②:労働者が労働の意思と能力を有していること
休業手当が支給されるには、労働者が「労働の意思と能力」を持ち、いつでも働ける状態にあることが前提となります。この手当は、本来働けるはずの労働機会を会社側の都合で奪われた労働者を保護するための制度です。
したがって、労働者自身の個人的な事情で働けない場合は、支給対象となりません。
- 労働者自身の病気やケガによる療養期間
- 労働組合の活動であるストライキへの参加(労働提供の意思がないため)
- 産前産後休業、育児休業、介護休業の取得期間(労働義務が免除されているため)
休業手当の計算方法(平均賃金の6割以上)
休業手当の額は、休業した日数に対し、平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。計算の基礎となる平均賃金は、原則として、休業日以前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数(暦日数)で割って算出します。
賃金総額には基本給のほか、残業手当や通勤手当などの諸手当も含まれますが、結婚手当など臨時の手当や3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は除外されます。パートタイマーなど労働日数が少ない労働者には、計算上の最低保障額が定められています。
具体的な計算手順は以下の通りです。
- 休業日以前3か月間の賃金総額を計算する。
- 上記3か月間の暦日数を計算する。
- 「賃金総額 ÷ 暦日数」で1日あたりの平均賃金を算出する。
- 「平均賃金 × 60%以上(会社の定めた支給率) × 休業日数」で休業手当の総額を計算する。
なお、1日のうち一部だけ休業させた場合、その日に支払った賃金が平均賃金の60%に満たないときは、差額分を支払う必要があります。
訴訟の最大の争点「使用者の責に帰すべき事由」の解釈
基本的な考え方:不可抗力との線引き
休業手当をめぐる紛争で最大の争点となるのが、休業の原因が「使用者の責に帰すべき事由」か、それとも「不可抗力」かの判断です。不可抗力と認められるには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
- その原因が事業の外部より発生した事故であること(外部起因性)
- 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること(防止不可能性)
このため、単なる不況や資材不足、機械の故障などは、会社に直接の非がなくても経営リスクの範囲内とみなされ、不可抗力とは認められません。労働基準法第26条の「責めに帰すべき事由」は、民法上の過失責任より広く、会社の経営管理の範囲内で発生した障害は原則としてすべて含まれると解釈されています。
「使用者の責」が認められやすいケースの具体例
会社の経営や管理の範囲内で発生した事由による休業は、原則として「使用者の責」が認められます。たとえ原因が外部にあったとしても、経営判断や事前の備えによって回避できた可能性がある場合は、会社都合と判断される傾向にあります。
- 経営上の理由: 業績悪化、受注減少、資金難、在庫過多による生産調整
- 管理上の理由: 原材料の調達不足、機械の故障・点検、配送ミス
- 取引関係の理由: 親会社の経営難による資金・資材供給の停止
- 派遣契約の理由: 派遣先から契約を打ち切られ、次の派遣先が見つからない
- 行政要請への対応: 法的強制力のない営業自粛要請に応じた自主的休業
「使用者の責」が認められにくいケースの具体例(自然災害など)
一方で、天災地変などの不可抗力によって、客観的に事業の継続が不可能な場合は、「使用者の責」にはあたらないと判断されます。休業の原因が会社の管理の及ばない外部にあり、かつ通常の注意を尽くしても回避できないことが要件となります。
- 天災地変: 地震や洪水で事業所が倒壊・浸水し、物理的に操業不可能な場合
- 交通機関の麻痺: 台風などで公共交通機関が全面的に運休し、従業員の出勤が物理的に不可能な場合
- 法令の遵守: 労働安全衛生法に基づき、健康診断の結果を受けて労働者を休業させる場合
- 行政処分・命令: 感染症法に基づく就業制限や、緊急事態宣言下での施設全体の閉館命令に従う場合
ただし、交通機関が動いているにもかかわらず、会社が自主的な判断で予防的に休業を命じた場合は、会社都合とみなされる可能性があります。
「休業回避努力」を尽くしたと証明するための記録と対応
不可抗力を主張するためには、会社が休業を回避するために最善の努力を尽くしたことを客観的な証拠で示す必要があります。単に状況を放置するのではなく、あらゆる代替手段を検討し、その過程を記録として残すことが極めて重要です。
- 在宅勤務やテレワークへの切り替えの可否を検討し、その議事録を残す
- 他部署への応援や配置転換を打診した記録を残す
- 業務内容を変更して、研修や教育訓練を実施した実績を残す
- 勤務時間の変更や有給休暇の取得を奨励した記録を残す
これらの検討内容を議事録や稟議書として保存しておくことで、労働基準監督署の調査や裁判において有力な証拠となります。
休業手当をめぐる重要な裁判例の解説
【判例解説】原材料・資金難など経営上の障害による休業
経営上の障害による休業について、最高裁判所は「ノースウエスト航空事件」で重要な判断を示しました。この判決では、労働基準法第26条の「責に帰すべき事由」は民法上の過失責任より広く、使用者側に起因する経営・管理上の障害をすべて含むとされました。
この基準により、原材料不足、資金難、販売不振といった事態は、たとえ会社に直接的な落ち度がなくても、企業経営に伴うリスクとみなされます。これらのリスクを労働者に転嫁することは許されず、会社側の責任として休業手当の支払い義務を負うという考え方が確立されています。
【判例解説】親会社の意向や行政勧告による事業停止
親会社の指示や行政からの勧告を原因とする事業停止も、原則として「使用者の責」と判断されます。例えば、親会社からの資金供給が停止して下請会社が操業不能になった場合、その取引関係は経営判断に基づくものであるため、不可抗力とは認められません。
同様に、監督官庁から操業停止の勧告を受けた場合も、勧告を受けるに至った管理体制そのものに会社の責任があると判断されます。また、法的強制力のない行政要請に応じた自主休業も、最終的な経営判断である以上、会社は労働者に対して休業手当の支払義務を負います。
【判例解説】機械の検査や改修、ストライキなどによる休業
自社の設備点検や労働紛争に起因する休業についても、判例の基準が存在します。機械の故障修理や定期検査に伴う休業は、設備の保守管理義務の範囲内であり、明確に「使用者の責」に該当します。
一方、ストライキの影響による休業は判断が分かれます。一部の組合員によるストライキが原因で、ストに参加していない他の従業員が働けなくなった場合、最高裁はノースウエスト航空事件で、会社側が誠実な交渉を行うなど信義則上相当な対応をしていれば、使用者の責にはあたらないと判断した事例があります。これは、労働者側の争議行為に起因する損失を会社に補償させるのは妥当ではないという考え方に基づきます。
なぜ裁判では賃金全額(10割)の支払いが命じられるのか
労働基準法第26条と民法第536条第2項の関係性
休業時の支払い義務を定める法律には、労働基準法と民法の2つがあり、それぞれ目的と内容が異なります。労働基準法はあくまで最低基準(6割以上)を定めた行政上の取締法規であり、これに違反すると罰則が科されます。
一方、民法は当事者間の契約ルールを定めており、第536条第2項では、会社(債権者)の責任で労働者が働けなくなった場合、労働者は賃金の全額(10割)を請求する権利を失わないと規定しています。労働基準法の手当を支払ったとしても、民法上の賃金請求権が消滅するわけではありません。したがって、労働者は差額の40%分を民事訴訟で請求することが可能です。
| 項目 | 労働基準法第26条(休業手当) | 民法第536条第2項(危険負担) |
|---|---|---|
| 目的 | 労働者の最低生活保障 | 私人間の契約上の公平性維持 |
| 支払い義務 | 平均賃金の6割以上 | 賃金の全額(10割) |
| 該当事由の範囲 | 経営上の障害など広範 | 故意・過失・信義則上の同視事由 |
| 性質 | 行政上の義務(強行法規) | 民事上の権利(契約上の権利) |
裁判所が賃金全額支払いを認める法的ロジック
裁判で賃金全額の支払いが命じられるのは、休業の原因が民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき事由」に該当するためです。この民法上の事由は、労働基準法より厳しく解釈され、使用者の故意・過失、またはそれに準ずる信義則上の事由がある場合に適用されます。
例えば、不当解雇が後に裁判で無効と判断された場合、解雇期間中に働けなかったのは会社の違法行為が原因であるため、会社は賃金の全額を支払う義務を負います。会社がこの10割支払いを免れるためには、就業規則などで民法の適用を排除する特約を設ける必要がありますが、その特約が労働者に一方的に不利益な内容である場合などは、裁判で無効と判断される可能性が高くなります。
休業手当の訴訟リスクと企業が取るべき予防・対応策
訴訟に発展した場合の金銭的・信用的リスク
休業手当の不払いが訴訟に発展すると、企業は深刻なダメージを受ける可能性があります。リスクは金銭的なものに留まらず、企業の社会的信用にも及びます。
- 金銭的リスク: 未払い賃金や手当に加え、法定利率による遅延損害金や、未払い額と同額の付加金(一種の制裁金)の支払いを命じられる可能性がある。
- 信用的リスク: 「ブラック企業」との評判が広まり、顧客離れや取引停止につながる恐れがある。
- 採用上のリスク: 企業イメージの悪化により、優秀な人材の確保が困難になる。
従業員とのトラブルを未然に防ぐための予防策
紛争を未然に防ぐためには、日頃からの誠実なコミュニケーションと社内体制の整備が不可欠です。
- 丁寧な説明: 休業を実施する際は、理由や期間、手当の基準を事前に詳しく説明し、従業員の理解を得る。
- 公的支援の活用: 雇用調整助成金などを活用し、法定を上回る手当の支給を検討する。
- 就業規則の整備: 休業時の取り扱いを就業規則に明確に規定し、法改正に合わせて定期的に見直す。
- 信頼関係の構築: 経営陣が従業員の雇用と生活を守る姿勢を明確に示し、良好な労使関係を維持する。
従業員から支払いを請求された場合の具体的な対応フロー
従業員から休業手当などを請求された場合は、迅速かつ冷静な初動対応が重要です。感情的な対応は避け、以下の手順で進めることが望まれます。
- 請求内容(期間、事由、金額)を書面で正確に確認する。
- 勤務記録や休業命令の経緯など、客観的な事実関係を徹底的に調査する。
- 顧問弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談し、法的見解を確認する。
- 自社に非がある場合は早期の和解を検討し、見解が異なる場合は法的根拠に基づき書面で回答する。
就業規則における休業手当規定の整備と民法適用の排除
会社都合休業時の支払い義務を平均賃金の60%に限定したい場合、就業規則にその旨を定めるだけでは不十分です。裁判で賃金全額(10割)の支払いを命じられるリスクを避けるには、民法第536条第2項の適用を排除する特約を明確に規定する必要があります。
ただし、このような規定を後から追加することは従業員にとっての不利益変更にあたる可能性があります。そのため、規定の変更には高度な合理性が求められ、専門家と相談の上で慎重に進める必要があります。
休業手当に関するよくある質問
パートタイマーやアルバイトにも休業手当を支払う義務はありますか?
はい、支払う義務があります。休業手当は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった雇用形態に関わらず、会社と雇用契約を結ぶすべての労働者が支給対象となります。
休業手当の支払いを怠った場合の罰則はありますか?
はい、あります。労働基準法第26条違反には、30万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性があります。また、民事訴訟では、未払い額に加えてそれと同額の付加金の支払いを命じられることがあります。
就業規則に規定がなくても支払う必要はありますか?
はい、支払う必要があります。休業手当の支払いは労働基準法に定められた強行法規であり、会社の義務です。そのため、就業規則に規定がない場合や、労働者と「支払わない」という合意があったとしても無効となり、法律に基づいて支払い義務が発生します。
休業手当と休業補償の違いは何ですか?
休業手当と休業補償は、発生原因や根拠法が全く異なる制度です。
| 項目 | 休業手当 | 休業補償 |
|---|---|---|
| 発生原因 | 会社都合による休業 | 業務上の負傷・疾病による療養 |
| 根拠法 | 労働基準法 第26条 | 労働基準法 第76条(労災保険法) |
| 支払い元 | 会社(使用者) | 労災保険(国) |
| 課税の有無 | 課税対象 | 非課税 |
まとめ:休業手当の訴訟リスクを回避する法的知識と実務対応
本記事では、休業手当の支給義務をめぐる法的争点、特に「使用者の責に帰すべき事由」の広範な解釈と、それに関する重要な裁判例を解説しました。経営難や資材不足といった経営上の障害は、不可抗力とは認められず、原則として会社の責任範囲と判断される点が重要です。また、労働基準法上の6割だけでなく、民法に基づき賃金全額の支払いを命じられるリスクも念頭に置く必要があります。訴訟トラブルを未然に防ぐためには、休業の必要性を慎重に判断するとともに、休業回避努力の記録を残し、従業員へ誠実な説明を尽くすことが不可欠です。万が一の事態に備え、平時から就業規則の整備や専門家への相談体制を構築しておくことが、企業防衛の鍵となります。