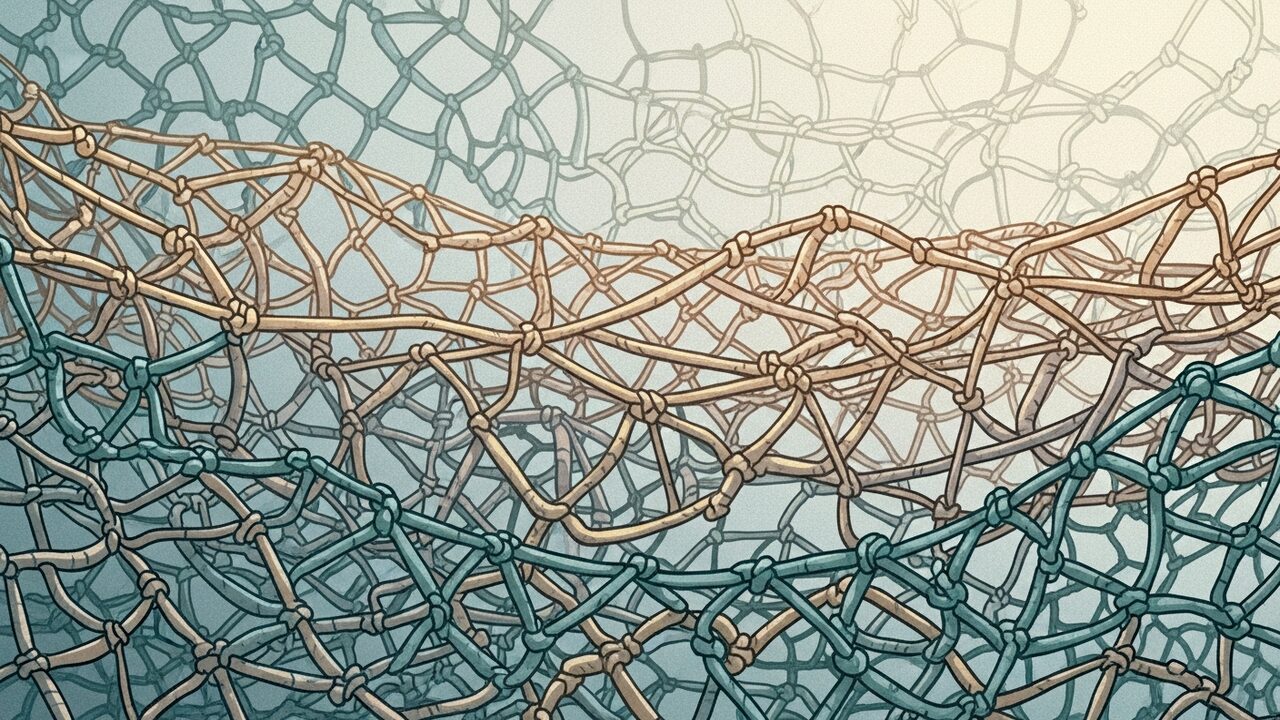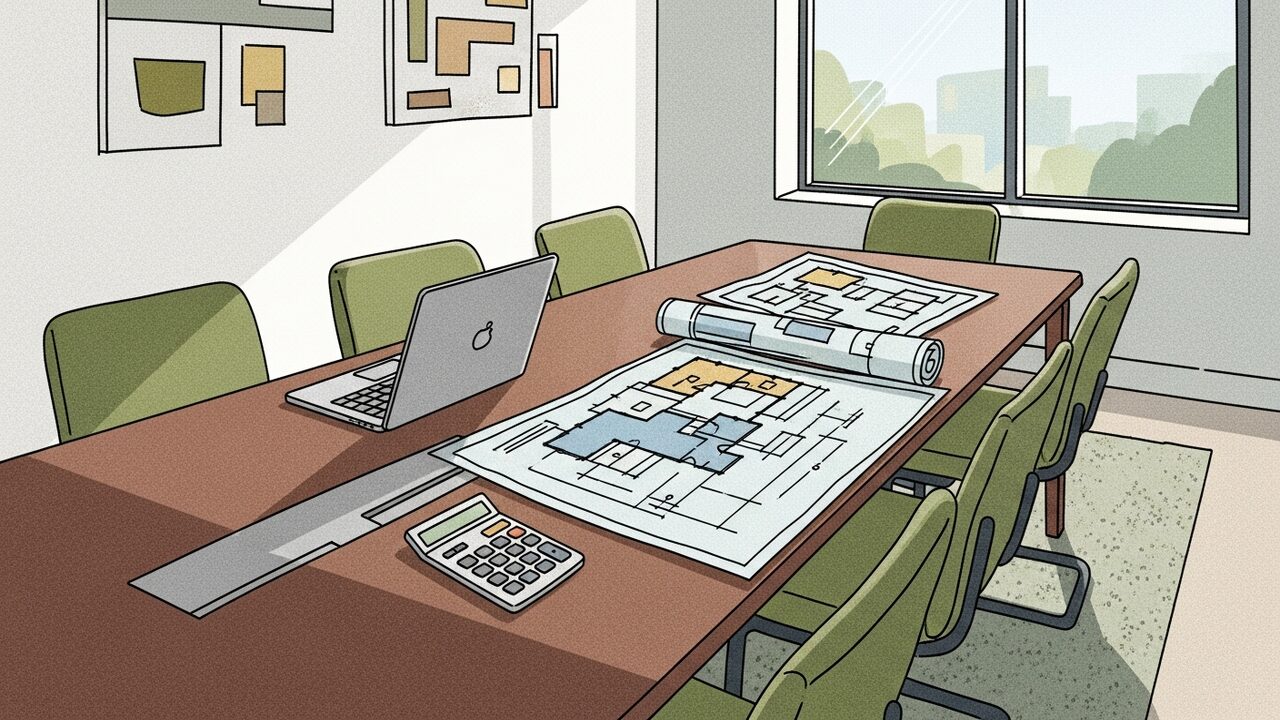減損損失の税務|法人税の損金算入要件と税効果会計を解説
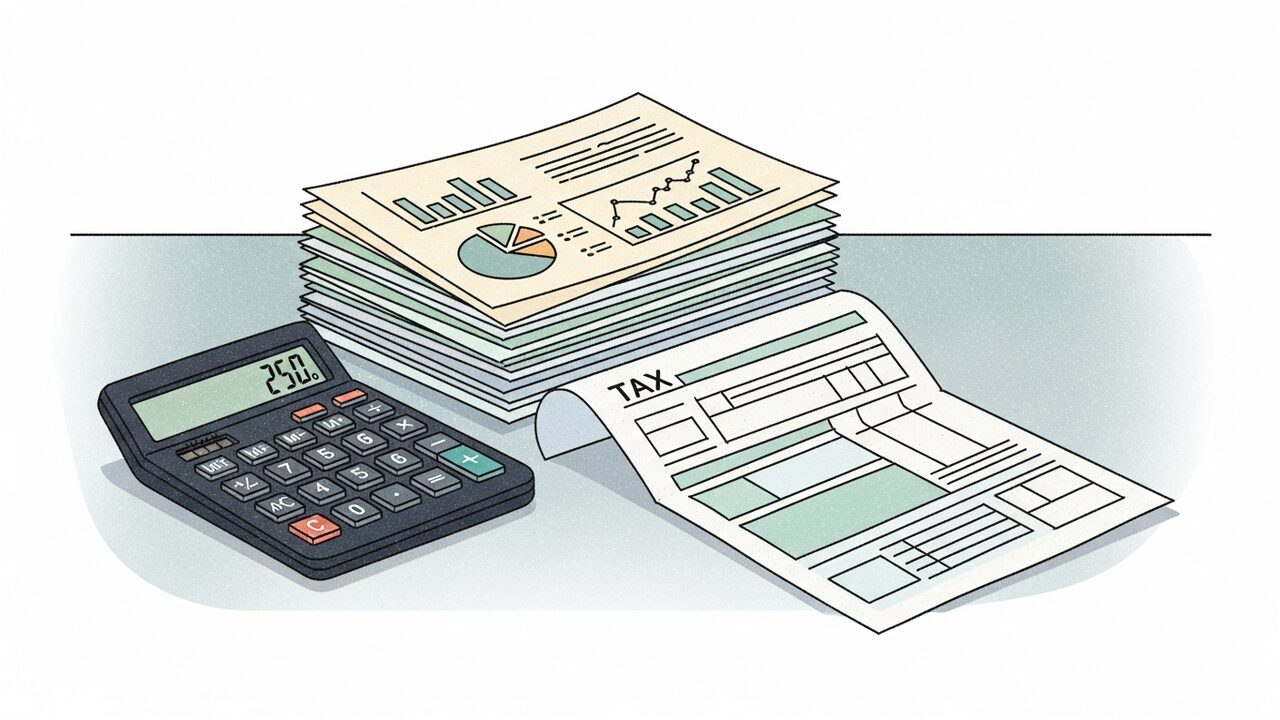
企業の重要な固定資産について減損処理を検討・実施する際、会計上の損失計上が法人税の計算上、どのように扱われるのかは経理・財務担当者にとって極めて重要な問題です。会計ルールと税法ルールでは資産評価の考え方が根本的に異なり、その差異を正しく理解しなければ適切な税務申告は行えません。この記事では、減損損失が法人税法上、損金として算入できるかの要件、損金不算入となる場合の申告調整、そして税効果会計の実務までを網羅的に解説します。
減損会計と法人税法の基本的な考え方の違い
会計における減損処理の目的と概要
会計上の減損処理とは、固定資産の収益性が低下し、投資額の回収が見込めなくなった場合に、その資産の帳簿価額を回収可能な金額まで引き下げる手続きです。この処理の主な目的は、資産の過大な帳簿価額を是正し、将来に損失を繰り延べないことで、財務諸表の信頼性を確保することにあります。上場企業や会社法上の大会社に適用される会計基準では、減損処理が義務付けられています。
減損処理は、以下の手順で進められます。
- 資産をキャッシュフローを生み出す最小単位でグルーピングします。
- 資産グループに減損の兆候があるかどうかを判定します。
- 兆候がある場合、帳簿価額と割引前の将来キャッシュフローを比較し、減損損失を認識すべきか判断します。
- 減損を認識すべきと判断された場合、帳簿価額を回収可能価額まで切り下げ、その差額を特別損失として計上します。
法人税法における固定資産評価損の原則(損金不算入)
法人税法では、法人が資産の評価換えによって帳簿価額を減額しても、その評価損は原則として損金に算入できないと定められています。これを「評価損の損金不算入の原則」と呼びます。税務では、資産価値の低下は譲渡や除却といった客観的な事実によって損失が実現するまで認識しないという取得原価主義が基本です。
この原則は、企業が恣意的に損失を計上して課税所得を操作し、租税回避を行うことを防ぐためのものです。そのため、会計上で減損損失を計上したとしても、税務申告の際にはその金額を所得に加算する申告調整が必要となります。税務上の資産価額は、減損処理が行われた後も取得価額を基礎とした帳簿価額が維持されます。
会計上の損失が税務上は原則として認められない理由
会計上の減損損失が税務上で原則として認められないのは、両者の目的や基準が根本的に異なるためです。会計が将来の予測を含むことで企業の財政状態をより実態に即して報告しようとするのに対し、税務は客観性と公平性を重視します。
| 項目 | 会計(減損処理) | 税務(評価損) |
|---|---|---|
| 目的 | 投資家保護(企業の財政状態や経営成績の適正な表示) | 課税の公平性(客観的な基準に基づく課税) |
| 判断基準 | 将来キャッシュフローの見積りなど、経営者の主観的・予測的な判断を許容 | 災害や法的整理など、客観的な事実に基づく債務確定主義が原則 |
| 評価単位 | 複数の資産をまとめた資産グループ単位が基本 | 個別資産単位が原則 |
| 価値の概念 | 将来の収益力に基づく「使用価値」を含む回収可能価額 | 第三者間で通常取引される客観的な「時価」 |
減損損失が税務上「評価損」として損金算入される要件
法人税法で損金算入が認められる評価損の概要
法人税法では、評価損の損金算入を原則として認めませんが、特定の事実が生じた場合には例外的に損金算入を認めています。法人税法第33条第2項では、災害による著しい損傷や政令で定める事実が発生し、資産の時価が帳簿価額を下回った場合に限り、損金経理を条件として評価損の計上が可能です。
損金算入が認められるのは、単なる市況の悪化や価格の下落ではなく、資産そのものの価値を低下させる予測不可能な事象が客観的に発生した場合に限られます。実務上、会計上の減損損失がこれらの税務要件を完全に満たすケースは限定的ですが、特定の条件下では減損損失の一部または全部が税務上の評価損として認められる可能性があります。
要件①:災害による損傷など物理的な要因(法人税法第33条第2項)
損金算入が認められる代表的な要件は、地震、火災、風水害などの災害によって固定資産が著しく損傷したことです。物理的な損傷により資産価値が帳簿価額を下回った場合、その評価損を損金に算入できます。
この要件で評価損を計上する際は、損傷の事実と、その時点での時価を客観的な資料で証明する必要があります。物理的な損壊があるため他の要件より証明しやすい側面がありますが、時価の算定は慎重に行わなければなりません。また、受け取った保険金などで補填される金額がある場合は、その額を損失額から差し引いて損金算入額を計算します。
要件②:1年以上の遊休状態など特定の事実(法人税法施行令第68条)
物理的な損傷がなくても、法人税法施行令第68条に定められた特定の事実が生じた場合には、例外的に評価損の損金算入が認められます。
- 資産が1年以上にわたり遊休状態にあり、今後も使用される見込みがないこと。
- 資産が本来の用途に使用できなくなり、他の用途に転用された結果、価値が著しく低下したこと。
- 資産が所在する場所の状況(地盤沈下など)が著しく変化し、利用価値が根本から損なわれたこと。
- 民事再生法による再生計画認可の決定など、法的に準ずる特別の事実があること。
これらのいずれも、単なる市場価格の変動や経済状況の悪化だけでは認められず、資産そのものを取り巻く環境に根本的な変化が生じていることが厳格に審査されます。
ソフトウェアや有価証券など資産別の留意点
資産の種類によって、評価損の判定には固有の留意点があります。
ソフトウェアの場合、物理的な消滅がなくても、特定の状況下で除却損として価値喪失が認められることがあります。ただし、法人税法上の評価損として損金算入が認められるケースは限定的です。
- 自社利用ソフトウェアが担っていた業務が廃止され、将来利用されることが客観的に明らかである場合。
- ハードウェアやOSの変更によって、従来のソフトウェアが利用不能となった場合。
有価証券については、市場価格の有無で基準が異なります。
- 上場有価証券:時価が取得価額のおおむね50%程度以上下落し、かつ近い将来の回復が見込まれない場合。
- 非上場株式:発行会社の財政状態が著しく悪化し、1株あたり純資産価額が取得時に比べておおむね50%以上下落した場合。
損金算入の要件を満たすことを証明するための客観的資料の準備
税務上の評価損として損金算入を認めてもらうためには、その要件を満たす事実を証明する客観的な資料が不可欠です。これらの資料は税務調査で事実関係を説明する重要な根拠となるため、申告後も適切に保管する必要があります。
- 災害による損傷:被災証明書、現場写真、修理業者の見積書、廃棄証明書など。
- 遊休・用途変更:使用中止を決定した取締役会の議事録や稟議書など。
- 時価の下落:不動産鑑定評価書、路線価や固定資産税評価額に基づく算定資料など。
- 有価証券:市場価格の推移を示す資料、発行会社の決算書、清算手続開始の通知書など。
損金不算入の場合に必要となる法人税の申告調整
申告調整の目的と会計・税務の差異の管理
会計上の利益と税務上の所得に差異が生じた場合、そのズレを調整して正しい税額を計算する手続きが申告調整です。減損損失は会計上費用となりますが、税務上は原則として損金にならないため、この差異を申告調整で修正します。
この会計と税務の差異は、将来解消される見込みがあるため「一時差異」として管理されます。減損が否認された資産は、会計上の帳簿価額と税務上の帳簿価額が異なる状態(二重の簿価)になります。この差異を帳簿外で適切に管理し、将来どのタイミングで損金として認められる(認容される)かを把握しておくことが重要です。
別表四における加算処理(減損損失の損金不算入)
会計上で計上した減損損失を税務上否認する場合、法人税申告書の別表四で所得に加算する処理を行います。具体的には、当期純利益を基点とし、「減損損失否認」などの項目で損金不算入額を加算します。これにより、課税所得が会計上の利益よりも大きくなります。
加算処理の方法は、資産の種類によって異なります。
- 償却資産(建物など):減損損失は、会計上の減価償却費とは別に、原則として全額が否認の対象となり、別表四で加算されます。
- 非償却資産(土地など):減価償却の概念がないため、計上された減損損失の全額が否認の対象となり、別表四で全額加算されます。
これらの加算額は、別表五(一)で利益積立金(いわゆる「税務上の純資産」)の増加として記録され、翌期以降に引き継がれます。
翌期以降の認容処理(減価償却や資産売却・除却時)
別表四で加算(否認)された減損損失は、将来、特定の事由が発生した時点で損金として認められます。これを認容処理といい、別表四で減算調整を行います。
認容されるタイミングも資産の種類によって異なります。
- 償却資産:減損後の会計上の減価償却費は、税務上の償却限度額を下回ります。この差額(償却不足額)の範囲内で、過去に否認された減損損失が毎期段階的に認容(減算)されます。
- 非償却資産:その資産を売却または除却した事業年度に、過去に否認されていた減損損失が実現損失として一括で認容(減算)されます。
この認容処理を正しく行うためには、固定資産台帳などで税務上の帳簿価額を別途管理し続けることが不可欠です。
減損処理に伴う税効果会計の具体的な実務
減損損失が「将来減算一時差異」となる仕組み
減損損失が税務上損金不算入となると、会計上の資産価額が税務上の資産価額よりも低くなります。この差額は、将来、減価償却や資産売却によって税務上の損金として認容され、その時点の課税所得を減らす効果を持ちます。このように、将来の税負担を軽減する効果を持つ一時差異を「将来減算一時差異」と呼びます。
税効果会計は、この将来の税金軽減効果を「繰延税金資産」という資産として当期の財務諸表に計上する会計処理です。これにより、会計上の利益と法人税等の負担を期間的に対応させ、財務報告の適正性を高めることができます。
繰延税金資産の計上と会計処理(仕訳例)
将来減算一時差異が発生した場合、その金額に法定実効税率(法人税、住民税、事業税の合計税率)を乗じて繰延税金資産の額を計算します。この繰延税金資産は貸借対照表の資産の部に計上され、相手勘定である「法人税等調整額」は損益計算書に計上されます。
例えば、1,000万円の減損損失が全額否認され、法定実効税率が30%の場合、300万円(1,000万円 × 30%)の繰延税金資産を計上します。仕訳は「(借方)繰延税金資産 300万円 / (貸方)法人税等調整額 300万円」となります。この法人税等調整額は税金費用をマイナスする効果があるため、当期純利益の減少は1,000万円ではなく700万円に緩和されます。
繰延税金資産の回収可能性の判断における重要ポイント
繰延税金資産を計上する上で最も重要なのが「回収可能性」の判断です。税金の軽減効果は、将来的に課税所得が発生して初めて意味を持ちます。したがって、将来的に利益が見込めず、課税所得が発生しないと予測される企業は、繰延税金資産を計上できません。
回収可能性の判断は、企業の過去の業績や将来の収益力に応じて行われます。減損損失を計上する企業は業績が悪化していることが多く、将来の合理的な見積可能期間(原則5年)内に発生する課税所得の範囲内でしか繰延税金資産を計上できないケースが少なくありません。特に、土地の減損など、解消時期が不明確な一時差異(スケジューリング不能な差異)については、原則として資産計上が認められないなど、厳格な判断が求められます。
回収可能性の判断における事業計画との整合性と社内承認プロセス
繰延税金資産の回収可能性を判断する際の将来課税所得の見積りは、企業の正式な事業計画に基づいている必要があります。外部監査では、その計画の合理性が厳しく検証されます。
- 将来の課税所得見積りは、取締役会などで承認された中長期計画や予算と整合している必要がある。
- 計画の合理性(過去の達成状況、市場環境の変化など)が客観的なデータで裏付けられているかどうかが問われる。
- 経理部門だけでなく、経営企画や営業などの関連部署と連携して数値を策定し、経営陣の承認を得る。
- 判断基準を社内でマニュアル化し、毎期継続的に同じ基準で検討していることを記録として残す。
減損損失の税務に関するよくある質問
減損損失を計上すると、税務調査で指摘されやすいですか?
減損損失を計上すると、損益計算書上の利益が大きく変動するため、税務署の関心を引きやすくなるのは事実です。特に、減損損失を税務上の評価損として損金算入している場合、その要件を満たしているか、時価算定の根拠は妥当かといった点が税務調査で厳しくチェックされます。
一方、会計上の減損損失を税務上全額否認し、正しく加算調整を行っている場合は、所得計算自体に誤りはないため、それが直接的な追徴課税のリスクになることは少ないでしょう。ただし、減損の背景にある業績悪化に関連して、他の取引(関連会社との取引や在庫評価など)に調査が及ぶ可能性はあります。いずれの場合も、減損処理の経緯や税務調整の内容を明確に説明できるよう、関連資料を整理しておくことが重要です。
のれんの減損について、税務上の取り扱いは他の固定資産と同じですか?
いいえ、のれんの減損は他の固定資産とは全く異なる取り扱いとなります。税務上の「のれん」は「資産調整勘定」と呼ばれますが、その扱いは会計上ののれんとは大きく異なります。
- M&Aの株式取得で生じる会計上ののれんは、税務上は資産として認識されず、その減損損失は一切損金に算入できません。
- 税務上ののれんである資産調整勘定は、非適格合併や事業譲渡など特定の取引で生じますが、減損という概念自体が存在しません。
- 資産調整勘定は、会計上の処理に関わらず、60か月間の均等償却が法律で強制されており、評価損の計上は認められません。
このため、会計上で「のれん」の減損を行っても、税務上は認められず、申告調整が必要になります。
中小企業に特有の減損税務のルールはありますか?
中小企業に特有の税法上の減損ルールはありませんが、会計実務や税務調査の観点でいくつか特徴があります。
- 会計:上場企業と異なり、厳格な減損会計基準の適用は強制されず、「中小企業の会計に関する指針」に基づき、より簡便的な判定が可能です。
- 税務:法人税法の原則は同じですが、中小企業者等の少額減価償却資産の特例などを利用している場合、会計と税務の簿価管理が複雑になることがあります。
- 税効果会計:適用していない中小企業が多く、その場合、減損損失を計上しても税務上の加算調整のみを行い、繰延税金資産は計上しません。
- 税務調査:経営者と会社の距離が近いため、減損が利益操作に利用されていないかという視点で、より慎重な事実確認と丁寧な資料準備が求められます。
まとめ:減損損失の税務処理は原則と例外の理解が鍵
本記事では、固定資産の減損損失に関する会計処理と税務処理の違いについて、網羅的に解説しました。会計上の減損損失は、投資家保護の観点から将来の収益性低下を財務諸表に反映させるものですが、税務上は課税の公平性を重視するため、原則として損金に算入されません。この目的の違いが、申告調整や税効果会計といった実務上の対応が必要となる根本的な理由です。
ただし、災害による損傷や1年以上の遊休状態といった、法人税法で定められた客観的かつ特別な事実がある場合に限り、例外的に評価損としての損金算入が認められます。損金算入を目指す場合は、その要件を満たすことを証明する客観的な資料を準備することが不可欠です。損金不算入となる場合は、別表四での加算調整と、将来の認容処理を見据えた税務上の簿価管理、そして税効果会計における繰延税金資産の回収可能性の慎重な判断が求められます。自社の状況がどのケースに該当するかを正確に把握し、適切な会計・税務処理を行いましょう。