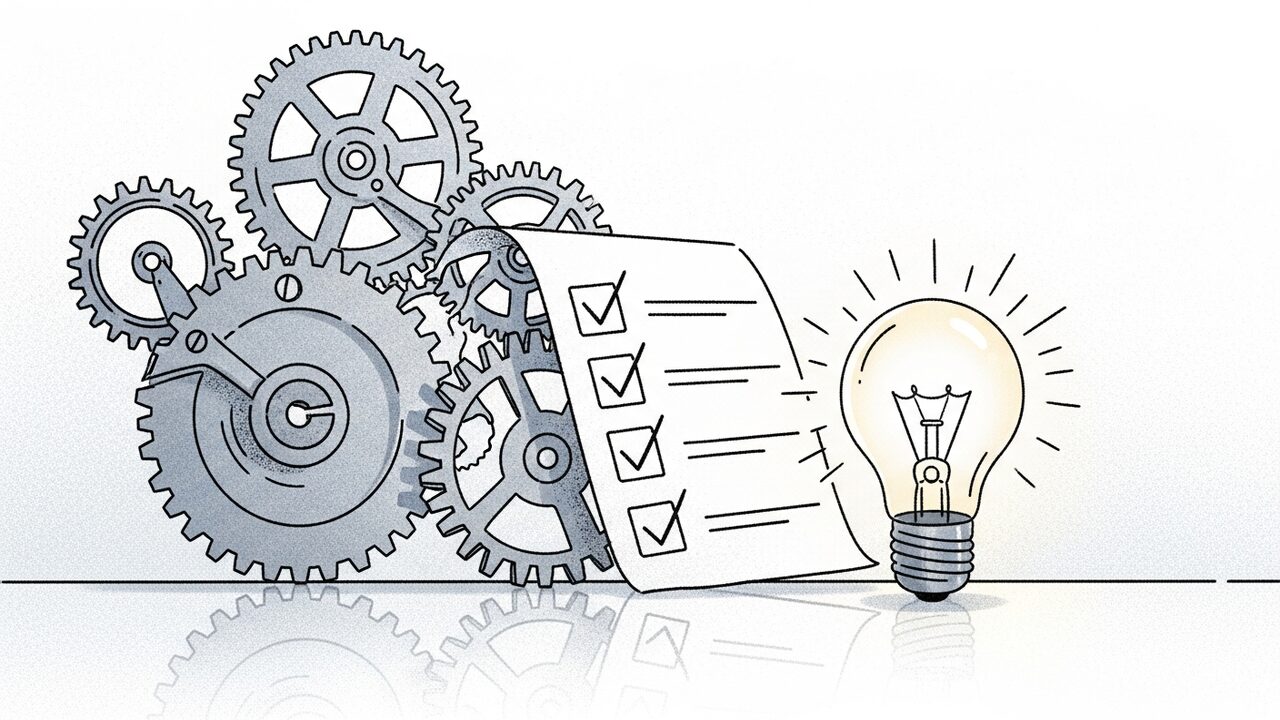弁護士費用は相手方に請求できるか?損害賠償として認められる範囲と法的根拠を解説

取引先とのトラブルにより訴訟や交渉を検討する際、発生する弁護士費用は経営上の大きな懸念事項となります。勝訴すれば、この費用を損害として相手方に請求できると考えるかもしれませんが、日本の法制度では原則として自己負担とされています。しかし、不法行為などの特定のケースでは例外的に請求が認められることもあります。この記事では、弁護士費用を損害賠償として相手方に請求できるかの法的根拠(原則と例外)、認められる金額の目安、そして最新の判例が実務に与える影響について詳しく解説します。
弁護士費用は原則自己負担|訴訟費用との違い
日本の裁判制度における弁護士費用負担の原則
日本の民事訴訟では、裁判にかかった弁護士費用は、原則として依頼した当事者がそれぞれ自己負担します。これは「各自負担の原則」と呼ばれ、たとえ裁判に勝訴したとしても、相手方に対して自身が支払った弁護士費用を請求することは基本的に認められていません。
この原則の背景には、日本の訴訟制度が「弁護士強制主義」を採用していないことがあります。つまり、当事者は弁護士に依頼せず、自分自身で訴訟を進めること(本人訴訟)が可能です。そのため、弁護士への依頼は当事者の任意による選択と解釈され、そこで発生する費用は、訴訟を行う上で不可欠なコストとは見なされないのです。
また、もし敗訴者が相手方の弁護士費用まで負担する制度になると、敗訴時のリスクが過大になり、正当な権利を持つ人でも訴訟提起をためらってしまう可能性があります。こうした「訴訟の萎縮」を防ぎ、誰もが司法にアクセスしやすくするという観点からも、各自負担の原則が採用されています。ただし、この原則には後述する例外が存在します。
「訴訟費用」と「弁護士費用」は異なるもの
実務上、「訴訟費用」と「弁護士費用」は混同されがちですが、法律上は全く異なるものです。民事訴訟法で敗訴者が負担すると定められている「訴訟費用」とは、裁判所に納める手数料や実費などを指し、弁護士に支払う報酬は含まれません。
判決で「訴訟費用は被告(相手方)の負担とする」とされても、それは収入印紙代などの実費を指すものであり、弁護士報酬を相手方が支払うという意味ではない点に注意が必要です。両者の違いは以下の通りです。
| 項目 | 訴訟費用 | 弁護士費用 |
|---|---|---|
| 根拠 | 民事訴訟費用等に関する法律 | 弁護士との委任契約 |
| 内容の例 | 収入印紙代、郵便切手代、証人の日当・旅費、鑑定費用など | 着手金、報酬金、日当、タイムチャージなど |
| 負担の原則 | 敗訴者負担(判決で負担者が指定される) | 各自負担(依頼者本人が負担する) |
| 相手方への請求 | 訴訟費用額確定処分の申立てを経て請求可能 | 原則として請求不可(例外あり) |
【例外】弁護士費用を損害として請求できる法的根拠とケース
不法行為に基づく損害賠償請求
弁護士費用が原則自己負担であることの最も重要な例外が、不法行為(例:交通事故、名誉毀損など)に基づく損害賠償請求です。この場合、被害者は加害者に対し、損害の一部として弁護士費用を請求することが判例上認められています(最高裁昭和44年2月27日判決)。
この判例では、被害者が加害者から賠償を受けるために、専門家である弁護士に依頼せざるを得ない状況を考慮しています。つまり、加害者の不法行為がなければ支払う必要のなかった弁護士費用は、不法行為と相当因果関係にある損害そのものである、と位置づけられるのです。
ただし、請求が認められるのは、実際に支払った全額ではなく、事案の難易度や認容された損害額などを考慮して「相当と認められる範囲」に限られます。実務上は、認容された損害賠償額の1割程度が弁護士費用相当の損害として認定される傾向にあります。例えば、損害額300万円が認められれば、その1割の30万円が上乗せされ、合計330万円の支払いが命じられます。
債務不履行に基づく損害賠償請求
契約違反、すなわち債務不履行を理由とする損害賠償請求では、原則として弁護士費用を相手方に請求することは認められません。契約当事者は、あらかじめ相手方の信用力や紛争リスクを予測して契約を締結できるため、紛争解決コストも織り込み済みと見なされるからです。
しかし近年、一部の裁判例では、その内容が不法行為と類似している場合や、訴訟の追行に高度な専門性が求められる場合には、例外的に弁護士費用の請求を認めることがあります。
- 労働災害における会社の安全配慮義務違反
- 医療過誤訴訟
- 建築瑕疵訴訟など、高度な専門知識を要する事案
これらのケースでは、本人だけで訴訟を進めることが著しく困難なため、不法行為と同様に弁護士への委任が不可欠と判断されやすい傾向にあります。ただし、単なる売買代金の未払いなど、一般的な契約違反では依然として請求は困難です。
契約書に弁護士費用の負担に関する特約がある場合
契約自由の原則に基づき、当事者間の合意によって、あらかじめ弁護士費用の負担について定めておくことが可能です。契約書に「本契約に関して紛争が生じた場合の弁護士費用は、違反した側が負担する」といった特約条項を設けておけば、それが請求の根拠となります。
このような特約は、特に企業間の取引において、紛争発生時のコスト負担を明確にし、債務不履行を抑制する効果が期待できます。裁判所も、特約が存在する場合には、原則としてその合意内容を尊重し、弁護士費用の請求を認める傾向にあります。
ただし、特約があれば無制限に請求できるわけではありません。裁判所は、請求額が社会通念上、合理的で相当な範囲内にあるかどうかを審査します。そのため、特約を設ける場合でも、認容額は損害額の1割程度を目安に判断されることが多いのが実情です。それでも、原則として請求が認められない債務不履行において、請求の根拠を作れるという点で特約の意義は大きいと言えます。
特約を設ける際の注意点と自社リスクの勘案
弁護士費用の負担に関する特約を契約書に盛り込む際には、いくつかの注意点があります。特に、契約の相手方や内容に応じて、その有効性やリスクを慎重に検討する必要があります。
- 消費者契約の場合: 消費者契約法により、事業者に一方的に有利な条項は無効と判断されるリスクがあります。
- 企業間取引の場合: 公序良俗や信義則に反する法外な費用負担を定める条項は、権利濫用として効力が否定される可能性があります。
- 文言の工夫: 「合理的な範囲内」や「相当と認められる額」といった限定的な表現を用いることが、条項の有効性を高めます。
- 自社のリスク: 双務的な特約は、自社が契約違反を犯した場合に、相手方の弁護士費用を負担する義務も生じさせる「諸刃の剣」です。
取引上の力関係が強い相手から一方的な負担条項を提示された場合は、修正交渉を試みることも重要です。特約を設ける際は、紛争発生の可能性や自社が負うリスクを総合的に勘案して判断すべきです。
債務不履行における弁護士費用請求の近年の動向(最高裁令和3年判決)
従来の判例における限定的な解釈
債務不履行に基づく損害賠償請求において、弁護士費用は損害に含まれない、というのが長年の判例の立場でした(大審院大正4年判決など)。特に金銭債務の不履行については、遅延損害金は民法所定の法定利率によって算定され、弁護士費用などの取立費用は別途請求できないとされてきました(最高裁昭和48年判決)。
この背景には、契約関係にある当事者は、取引開始時に相手方のリスクを評価し、それを契約条件に反映させることが可能であるという考え方があります。そのため、債権回収にかかる費用は、事業活動に伴う通常のコストの一部と見なされてきました。
前述の安全配慮義務違反などのケースで例外的に請求が認められる下級審裁判例は存在したものの、それらはあくまで特殊な事案に限られていました。一般的な売買契約などでは、特約がない限り弁護士費用は自己負担というのが実務上の共通認識でした。
最高裁令和3年1月22日判決の概要と判断基準
このような状況下で、最高裁令和3年1月22日判決は、債務不履行における弁護士費用請求について、改めて否定的な判断を示しました。この事案は、土地の売買契約で売主が所有権移転登記等を履行しなかったため、買主が訴訟を提起し、その弁護士費用を損害として請求したものです。
最高裁は、この請求を認めませんでした。その理由として、契約上の義務の履行を求めることは、不法行為のように侵害された権利の回復ではなく、あくまで契約目的の実現を目指すものであるという性質の違いを指摘しました。また、土地の引渡しや登記といった債務の内容は契約から明確に定まるものであり、事実関係が複雑な不法行為とは異なり、訴訟追行に弁護士の援助が不可欠とまでは言えないと判断したのです。
この判決により、一般的な契約上の義務の履行を求める訴訟において、弁護士費用を損害として相手方に請求することは、判例法理上、原則として認められないことがより明確になりました。
判例変更が企業間の契約実務に与える影響
最高裁令和3年判決は、企業間の契約実務において、紛争時のコスト負担に関する契約条項の重要性を改めて浮き彫りにしました。特段の合意がない限り、債務不履行を理由に相手方の弁護士費用を回収することは極めて困難であると法的に確認されたためです。
この判決を受けて、企業が実務上考慮すべき点は以下の通りです。
- 契約書における弁護士費用負担特約の重要性が増大した。
- 特約がない限り、債務不履行での弁護士費用回収は極めて困難であることが確認された。
- 費用倒れのリスクが高まり、訴訟提起の判断がより慎重になった。
- 訴訟以外の紛争解決手段(交渉、ADR)や予防法務(与信管理、契約書審査)の重要性が高まった。
今後は、紛争リスクが高い取引などでは、自衛策として弁護士費用負担に関する特約を契約書に盛り込むことが、これまで以上に重要な経営判断となります。
請求が認められる弁護士費用の金額と算定基準
損害額の1割程度が目安とされる理由
不法行為などで弁護士費用の請求が認められる場合でも、実際に支払った全額が損害として認定されるわけではありません。実務上は、裁判で認容された損害賠償額(元本)の1割程度が、相当な弁護士費用として認められることが一般的です。
この「1割基準」が採用されるのは、公平性と予測可能性を確保するためです。弁護士報酬は依頼者と弁護士との間の契約で自由に決められるため、その金額は様々です。もし実費全額を相手方に負担させると、相手方にとっては予測不能な過大な負担となりかねません。
そこで裁判所は、個別の委任契約の内容に立ち入ることなく、客観的かつ公平な基準として、認容額に応じた一定の割合を「相当因果関係のある損害」と認定する運用を定着させました。その結果、過去の報酬基準なども参考に、認容額の10%程度が実務上の目安として広く受け入れられています。
実際の裁判例から見る認容額の傾向と考慮要素
「1割」はあくまで目安であり、実際の裁判では、事案の個別事情に応じて柔軟に判断されます。昭和44年の最高裁判決が示した通り、裁判官は様々な事情を総合的に考慮して、相当な金額を裁量で認定します。
- 事案の難易度: 事実関係の複雑さ、立証の困難さ、専門性の高さなど。
- 請求額および認容額: 実際に認められた損害賠償額の大きさ。
- 審理の経過: 訴訟にかかった期間や労力。
- その他諸般の事情: 早期に和解したか、判決まで争ったかなど。
例えば、医療過誤訴訟など極めて専門的で立証が困難な事案では1割を超える額が認められることがあります。逆に、認容額が数億円と非常に高額になる場合は、1割を下回る割合に調整されることもあります。
弁護士費用全額の請求が認められにくい背景
被害者の立場からすれば、かかった弁護士費用は全額相手方に負担してほしいと考えるのが自然です。しかし、日本の司法制度では、以下の背景から全額請求は認められにくくなっています。
- 弁護士強制主義の不採用: 日本では本人訴訟が認められており、弁護士への依頼は当事者の任意であるため、その費用を当然に相手方に転嫁することはできないと考えられています。
- 相手方の裁判を受ける権利への配慮: 敗訴した場合に相手方の高額な弁護士費用まで負担するとなると、訴えられた側が正当な反論をすることを躊躇し、防御権の行使が萎縮してしまうおそれがあります。
- 弁護士報酬の自由化: 弁護士報酬は各法律事務所が自由に設定できるため、高額な報酬契約をそのまま相手方に負担させることは公平性を欠くと考えられています。
これらの理由から、被害者の救済と、相手方の負担のバランスを取るため、客観的に見て相当な範囲に限定される運用となっているのです。
実務上の注意点|訴訟・交渉におけるポイント
訴訟で弁護士費用を請求する際の主張・立証方法
訴訟において弁護士費用を損害として請求する場合、裁判所が職権で認めてくれるわけではないため、訴状できちんと主張する必要があります。具体的な手順は以下の通りです。
- 訴状の「請求の趣旨」で、元本となる損害額に弁護士費用相当額を加算した総額の支払を求める。
- 訴状の「請求の原因」で、不法行為等により訴訟提起を余儀なくされ、弁護士費用が発生した事実を主張する。
- 主張する弁護士費用額は、一般的に元本の1割程度を目安として記載しておく。
- 証拠として委任契約書の提出は必須ではありませんが、弁護士に委任している事実自体が、弁護士費用発生の立証の基礎となります。
最終的に認められる金額は、判決時に裁判所が認容する損害額に基づいて判断されることになります。
示談交渉の段階で弁護士費用を請求する場合の進め方
訴訟前の示談交渉の段階で、弁護士費用を請求することは実務上容易ではありません。交渉はあくまで当事者間の任意の話し合いであり、相手方(特に保険会社など)は「裁判になっていない以上、支払う義務はない」という立場を取ることがほとんどです。
しかし、交渉戦略として弁護士費用を含めた金額を請求することには意味があります。「このまま交渉が決裂して訴訟になれば、遅延損害金に加えて弁護士費用も上乗せされる可能性がある」と相手方に示すことで、譲歩を引き出し、早期解決を促すための交渉材料となり得ます。
ただし、示談や和解は「互譲の精神」に基づくため、双方が弁護士費用は各自で負担するという条件で合意することも少なくありません。弁護士費用の回収に固執しすぎると、かえって解決が遠のくリスクもあるため、早期解決のメリットと天秤にかけ、柔軟な対応をすることが重要です。
経営判断を仰ぐ際の費用回収リスクに関する説明ポイント
法務担当者が経営陣に対して訴訟提起の承認を求める際には、弁護士費用の回収リスクについて、正確かつ客観的な情報を提供することが不可欠です。感情論ではなく、経済的合理性に基づいた判断を促すため、以下の点を明確に説明する必要があります。
- 原則の説明: 勝訴しても弁護士費用は原則自己負担であり、回収できるのは例外的なケースに限られることを伝える。
- 回収見込額の提示: 回収が認められる場合でも、認容損害額の1割程度が目安であり、全額回収はできないことを具体的に示す。
- 費用倒れリスクのシミュレーション: 弁護士費用の支出総額と、回収可能な金額(元本+遅延損害金+弁護士費用)を比較し、経済的合理性を検討する。
- 回収不能リスク: 相手方の資力によっては、たとえ勝訴判決を得ても強制執行ができず、全く回収できない可能性があることを指摘する。
- 間接的コスト: 訴訟にかかる時間、担当者の工数、取引関係への影響、風評リスクなどの金銭以外のコストも併せて説明する。
これらの情報を基に、単なる勝ち負けだけでなく、最終的なキャッシュフローへの影響や、訴訟を行うことの経営上の意義(コンプライアンス遵守の姿勢を示すなど)を総合的に議論し、判断を仰ぐことが求められます。
弁護士費用の損害賠償請求に関するよくある質問
弁護士費用を損害として請求できる法的根拠(民法の条文)は何ですか?
民法には「弁護士費用を損害として請求できる」と直接定めた条文はありません。その根拠は、民法709条(不法行為による損害賠償)や民法415条(債務不履行による損害賠償)に定められた「損害」の範囲をどう解釈するかという、判例法理に基づいています。
最高裁判所は、不法行為の被害者が権利を守るために訴訟を起こさざるを得なくなった場合、そのために必要な弁護士費用は、加害行為と相当因果関係(民法416条参照)のある損害の一部であると判断しました。つまり、条文に書かれた「損害」という言葉の中に、例外的に弁護士費用も含まれる場合がある、という司法の解釈によって運用されています。
契約書に弁護士費用負担の条項を入れる際の文例を教えてください。
契約書に弁護士費用負担の条項を設ける際の一般的な文例は以下の通りです。重要なのは、過大な請求と見なされないよう、合理性の観点から文言を工夫することです。
【文例】 「甲または乙が本契約に違反したことにより、相手方がその権利を保全または行使するために、弁護士その他専門家への依頼を余儀なくされた場合、違反した当事者は、相手方が負担した合理的な範囲内の弁護士費用その他の費用を負担するものとする。」
【ポイント】
- 「合理的な範囲内」という文言を入れることで、条項が無効と判断されるリスクを低減します。
- 「訴訟に至った場合」に限定せず「権利を保全または行使するために」とすることで、交渉段階の費用も対象に含めることを意図できます。
不当訴訟を提起された場合、その対応費用も請求できますか?
原則として、裁判を起こすことは国民に保障された権利であり、たとえ敗訴したとしても、それ自体が違法行為になるわけではありません。したがって、訴えられた側が応訴のために支払った弁護士費用を、訴えてきた相手(原告)に請求することはできません。
ただし、極めて例外的なケースとして、訴えの提起が客観的に見て全く勝ち目がなく、相手方を害する目的(嫌がらせなど)でなされたと認められる場合には、その訴訟提起行為自体が不法行為(不当訴訟・濫訴)にあたることがあります。その場合、応訴のためにやむを得ず支出した弁護士費用を損害として、別途、損害賠償を請求(反訴など)することが可能です。しかし、不当訴訟と認定されるためのハードルは非常に高く、単に「請求が棄却された」というだけでは認められません。
まとめ:弁護士費用の請求可否は法的根拠の理解と事前の備えが鍵
この記事では、訴訟等で発生した弁護士費用を相手方に請求できるかについて解説しました。日本の法制度では弁護士費用は原則自己負担であり、勝訴しても相手方への請求は認められません。例外的に、不法行為に基づく損害賠償請求では「認容された損害額の1割程度」を目安に請求が認められる判例がありますが、一般的な債務不履行では極めて困難です。この原則は最高裁の近年の判例でも再確認されており、企業実務においては、紛争時のコストを相手方に転嫁するためには契約書にあらかじめ「弁護士費用負担の特約」を設けておくことが唯一かつ最も有効な自衛策となります。訴訟を検討する際は、費用倒れのリスクを十分に吟味し、契約書のレビューといった予防法務の重要性を認識することが不可欠です。