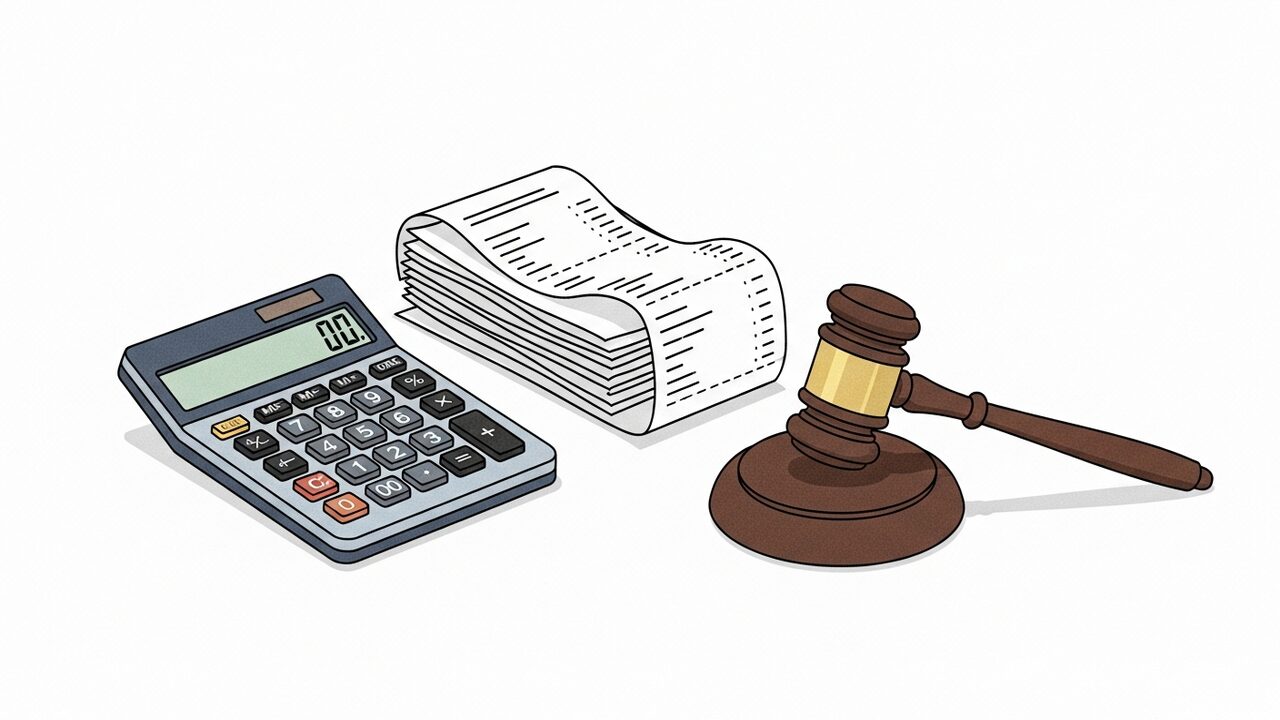特許異議申立てとは?無効審判との違い、手続きの流れ、費用を解説

競合他社の特許が成立し、自社の事業展開に影響が及ぶのではないかと懸念されている方もいらっしゃるでしょう。その特許の有効性に疑義がある場合、特許庁に対して見直しを求める手段として「特許異議申立て」という制度があります。この記事では、特許異議申立て制度の目的や要件といった基本から、無効審判との違い、具体的な手続きの流れ、費用の目安までを網羅的に解説します。本記事を通じて制度の全体像を正確に理解し、自社として取るべき戦略的なアクションを判断するための一助としてご活用ください。
特許異議申立てとは?制度の概要
制度の目的と趣旨
特許異議申立制度は、特許権の設定登録後、一定期間内に限り、第三者が特許付与の妥当性について見直しを求めることができる制度です。審査官による厳格な審査を経ても、調査漏れなどにより瑕疵のある特許が成立する可能性は皆無ではありません。そこで、公衆の協力を得て特許庁自らが処分の適否を再審理し、誤りがあれば是正することで、特許制度全体の信頼性を高めることを目的としています。個別の権利紛争の解決よりも、公益的な観点から特許の質を確保する点に重きが置かれています。
申立てができる者(申立人適格)
本制度は公益性の確保を目的とするため、申立てを行える者の範囲に厳しい制限はありません。特許法第113条では「何人も」申立てができると規定されており、利害関係の有無を問わず、誰でも申立人になることができます。
- 原則: 事業上の利害関係を問わず、個人・法人を問わず誰でも申立てが可能です。
- 匿名性: 申立書には氏名や名称の記載が必要なため、完全な匿名での申立てはできません。
- 実質的な匿名確保: 実務上、弁理士などを代理の申立人(ダミー)として立てることで、真の申立人の名前を伏せたまま手続きを進めることが可能です。
申立ての対象となる特許
異議申立ては、特許庁の審査を経て設定登録され、特許掲載公報が発行された特許を対象とします。複数の請求項がある場合でも、その一部のみを対象として申立てを行うことができます。
- 対象となる特許: 特許掲載公報が発行された後の登録特許が対象です。
- 対象範囲の指定: すべての請求項ではなく、自社の事業に関連する特定の請求項のみを対象とすることが認められています。
- 対象外となる特許: 権利が放棄されたり、存続期間が満了したりして消滅した特許権は申立ての対象外です。
申立てが可能な期間(申立期間)
特許異議の申立てができる期間は、特許掲載公報の発行日から6ヶ月以内と厳格に定められています。この期間は不変期間であり、いかなる理由があっても延長は認められません。これは、特許権者の法的地位を長期間不安定な状態に置くことを避け、権利の早期安定化を図るための規定です。したがって、申立てを検討する場合は、迅速な証拠収集と書面作成が求められます。
申立ての理由として認められる事由(取消理由)
異議申立てで主張できる理由は、公益性の観点から特許法に定められた取消理由に限定列挙されています。これらは主に、審査段階での見落としを指摘するものです。一方で、権利の帰属に関する当事者間の争いは、本制度の対象外です。
- 新規性や進歩性の欠如など、特許を受けるための要件(特許要件)を満たしていないこと。
- 明細書や特許請求の範囲の記載が、実施可能要件やサポート要件などの記載要件に違反していること。
- 先願主義に違反していること。
- 外国人の権利享有に関する規定に違反していること。
特許異議申立てと無効審判の比較
目的と審理の性格の違い
特許異議申立てと無効審判は、共に特許の有効性を争う手続きですが、その目的や性格は大きく異なります。異議申立てが特許庁による行政処分的な見直しという公益的な性格を持つのに対し、無効審判は当事者間の私的な紛争解決を目的としています。この違いが、手続きの様々な側面に影響を与えています。
| 項目 | 特許異議申立て | 無効審判 |
|---|---|---|
| 目的 | 公益目的(特許庁による処分の見直し) | 私益目的(当事者間の紛争解決) |
| 申立人/請求人 | 何人も可能 | 原則として利害関係人のみ |
| 申立/請求期間 | 特許掲載公報の発行日から6ヶ月以内 | 権利存続中および消滅後も請求可能 |
| 審理方式 | 書面審理が原則(職権主義が強い) | 口頭審理が原則(当事者主義が強い) |
| 不服申立て | 申立人は維持決定に不服申立て不可 | 当事者双方が審決に不服申立て可能 |
申立人(請求人)の資格要件の違い
異議申立ては、公益的な観点から「何人も」行うことができ、申立人が特許と直接の利害関係を持つ必要はありません。一方、無効審判を請求できるのは、原則としてその特許の存在によって権利や利益が影響を受ける「利害関係人」(例:侵害警告を受けた者、同業他社など)に限定されます。このため、事業準備段階など利害関係を証明しにくい状況では、異議申立てが有効な手段となります。
申立て(請求)ができる期間の違い
期間の制約にも明確な差があります。異議申立ては、特許掲載公報の発行日から6ヶ月以内という短い期間に限定されています。この期間を過ぎてしまうと、異議申立ては一切できなくなります。対照的に、無効審判は特許権が存続している間はいつでも請求でき、権利が消滅した後でも、過去の侵害行為に対する損害賠償請求に対抗するなどの目的があれば請求が可能です。
審理方式(職権審理と当事者審理)の違い
審理の進め方では、異議申立ては手続きの迅速化を図るため、原則として書面審理のみで行われます。また、審判官が申立人の主張に拘束されず、職権で証拠を調査したり、申立てにない理由を取り上げたりできる職権主義の色彩が強いのが特徴です。一方、無効審判は、当事者双方が対等な立場で主張・立証を尽くす口頭審理が原則であり、当事者主義に基づいた運用がなされます。
決定後の不服申立て手続きの違い
特許庁の判断に対する不服申立ての可否も重要な相違点です。異議申立てで特許を維持する決定が下された場合、申立人はその決定を不服として裁判で争うことはできません。一方、無効審判では、審決(特許庁の最終判断)に対して、敗訴した当事者の双方が知財高等裁判所へ出訴し、その妥当性を争うことができます。ただし、異議申立てで敗れても、別途無効審判を請求することは可能です。
特許異議申立てを行うメリット・デメリット
特許異議申立ての主なメリット
特許異議申立てには、無効審判にはない独自のメリットがあります。特に、申立人の匿名性確保やコスト面での優位性が挙げられます。
- 匿名性の確保: 代理人を申立人とすることで、自社の名前を明かさずに競合他社の特許を攻撃できます。
- 費用の低廉さ: 特許庁に納付する手数料が無効審判に比べて安価で、利用のハードルが低いです。
- 手続き負担の軽減: 書面審理が原則であるため、口頭審理への出頭が不要で、遠隔地の企業でも利用しやすいです。
特許異議申立ての注意点とデメリット
多くのメリットがある一方で、制度上の制約から生じるデメリットも存在します。これらを理解した上で、手続きを選択する必要があります。
- 不服申立ての制限: 特許維持決定が出た場合、申立人は不服を申し立てることができず、その手続きは終了します。
- 申立期間の短さ: 公報発行から6ヶ月という期間は、十分な証拠収集や分析を行うにはタイトな場合があります。
- 主張方法の制約: 書面審理のみであるため、複雑な技術内容を口頭で補足説明したり、審判官の心証に応じて主張を調整したりすることが困難です。
申立てをすべきか?実行前の判断ポイント
異議申立てを行うかどうかの判断は、自社の事業戦略や対象特許の重要性などを総合的に勘案して慎重に行うべきです。
- 事業への影響: 対象特許が自社の現在または将来の事業にとって、どの程度の障害となるか。
- 期間的要件: 公報発行日から6ヶ月以内という申立期間を満たしているか。
- 戦略的意図: 自社の関与を相手に知られたくないか、それとも徹底的に争う姿勢を示すべきか。
- 証拠の確度: 新規性や進歩性を覆すだけの強力な証拠を準備できるか。
- コストと時間: 予算や、解決までに許容できる期間はどの程度か。
特許異議申立ての手続きと流れ
申立て前の準備:無効理由の調査と証拠収集
申立ての成否は、事前の準備で大半が決まります。まず、対象特許の請求項を分析し、その有効性を否定できる先行技術文献(特許公報、論文など)を徹底的に調査します。申立期間経過後に新たな理由や証拠を追加することは原則として認められないため、最初の申立書で主張と立証を尽くす必要があります。必要に応じて比較実験データを用意するなど、盤石な論理構成を構築することが重要です。
申立書の提出と方式審査
調査と証拠収集が完了したら、法定期間内に「特許異議申立書」を特許庁に提出します。申立書には、申立人、対象特許、申立ての理由、証拠などを記載します。提出された書類は、まず手数料納付や記載事項の不備がないか方式審査を受けます。この審査を通過すると、申立書の副本が特許権者に送付され、特許権者は初めて異議申立てがあったことを知ります。
審理官による審理と取消理由の通知
方式審査を通過すると、3名または5名の審判官からなる合議体によって実体的な審理が開始されます。審理は提出された書面を中心に行われ、審判官は申立人の主張だけでなく、職権で発見した証拠も踏まえて特許の有効性を判断します。審理の結果、特許を取り消すべき理由があると判断した場合、特許権者に対して「取消理由通知」が送付されます。
特許権者による意見書・訂正請求の提出
取消理由通知を受け取った特許権者には、反論の機会が与えられます。指定された期間内(通常60日)に、審判官が指摘した取消理由に対する反論をまとめた「意見書」を提出できます。また、同時に特許請求の範囲を減縮したり、誤記を訂正したりすることで取消理由を解消するための「訂正請求」を行うことも可能です。これは権利を守るための非常に重要な手続きです。
審理の終結と決定(維持または取消)
特許権者から意見書や訂正請求書が提出されると、審判官はそれらの内容を審理し、必要に応じて申立人に再反論の機会を与えます。双方の主張が出揃った段階で、合議体は最終的な判断を下します。特許の取消理由が解消されたと判断されれば「維持決定」が、解消されなければ「取消決定」がなされ、その決定書が双方に送達されて手続きは終結します。
特許異議申立てにかかる費用の目安
特許庁に納付する手数料(印紙代)
特許庁へ納付する手数料は、基本料金と、申立ての対象とする請求項の数に応じた加算料金で構成されます。無効審判と比較して低廉に設定されています。
- 基本料金: 16,500円
- 加算料金: 請求項の数 × 2,400円
例えば、3つの請求項を対象として申し立てる場合の手数料は、16,500円 + (3 × 2,400円) = 23,700円となります。
弁理士に依頼する場合の代理人費用
弁理士に手続きを依頼する場合、上記の手数料とは別に代理人費用がかかります。費用は事務所や案件の難易度により異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
- 着手金(調査・申立書作成): 案件の複雑さに応じ、数十万円程度が一般的です。
- 中間対応費用: 特許権者からの反論に対応して意見書を作成する場合などに、追加で費用が発生することがあります。
- 成功報酬: 特許の取消しや権利範囲の減縮に成功した場合に、成果に応じて発生します。
特許異議申立てに関するよくある質問
特許異議申立ての成功率はどの程度ですか?
統計上、申立てによって特許が完全に取り消される割合は1〜2割程度ですが、特許権者が自ら権利範囲を狭める「訂正」を行うケースも多くあります。訂正によって結果的に自社製品が権利範囲から外れるなど、実質的に申立ての目的を達成できるケースを含めると、申立てが何らかの成果につながる割合はより高くなります。単なる取消率の数字だけでなく、戦略的な有効性を評価することが重要です。
申立人は匿名で手続きを進めることは可能ですか?
申立書に申立人の氏名・住所の記載が必須であるため、制度上、完全な匿名での申立てはできません。しかし、実務では弁理士や協力者など第三者を代理の申立人(通称「ダミー」)として立てることが広く行われています。これにより、特許権者に真の利害関係者を知らせることなく、実質的に匿名性を保ったまま手続きを進めることが可能です。
申立てが認められなかった場合、その後はどうなりますか?
特許異議申立てで「維持決定」が下されると、申立人はその決定に対して不服を申し立てることはできず、手続きは確定します。ただし、この決定は特許の有効性を最終的に確定させるものではありません。申立人は、異議申立てとは別に「無効審判」を請求し、再度同じ特許の有効性を争うことができます。その際は、異議申立てでの審理内容を踏まえ、より強力な証拠や新たな論点を準備して臨むことになります。
申立期間(6ヶ月)を過ぎた場合、他に手段はありますか?
特許掲載公報の発行日から6ヶ月の申立期間を過ぎてしまった場合、特許異議申立ては利用できません。その後の手段としては、主に「無効審判」の請求が考えられます。ただし、無効審判を請求するには原則として「利害関係人」である必要があります。また、審理を求めるものではありませんが、審査の質向上に協力する観点から、特許の有効性に疑義がある資料を特許庁に提供する「情報提供制度」を利用することも可能です。
手続きは自社のみで行うべきか、弁理士に依頼すべきですか?
手続きを自社で行うことも法的には可能ですが、弁理士への依頼を強く推奨します。異議申立ては、先行技術文献を的確に評価し、特許法上の取消理由に沿って論理的な主張を書面で構築する必要があります。また、特許権者による専門的な反論や訂正請求に適切に対応するには、高度な専門知識と実務経験が不可欠です。成功の確率を高めるためには、専門家である弁理士の知見を活用することが極めて重要です。
まとめ:特許異議申立てを戦略的に活用するために
本記事では、特許異議申立て制度について、その概要から無効審判との違い、具体的な手続きまでを解説しました。この制度は、公報発行後6ヶ月以内という期間制限はありますが、「何人も」申立てが可能で、代理人を立てることで匿名性を確保できるなど、戦略的に活用できるメリットがあります。一方で、維持決定に対する不服申立てができないといった制約もあり、期間を過ぎた場合や徹底的に争いたい場合は無効審判が選択肢となります。対象特許が自社の事業に与える影響を評価し、有力な証拠が見つかった場合は、申立期間を逃さないよう迅速な判断が求められます。手続きには高度な専門性が要求されるため、具体的なアクションを検討する際は、まず弁理士などの専門家に相談し、最適な戦略を立てることが成功の鍵となります。