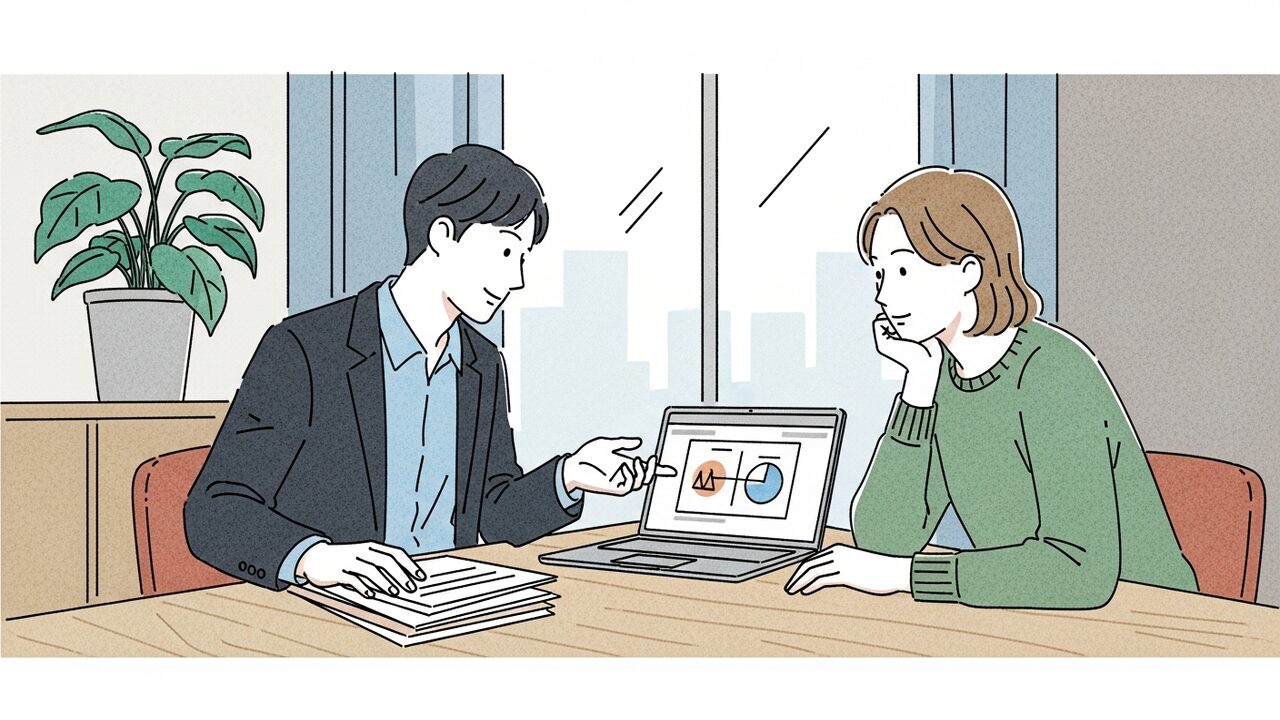損害賠償命令制度とは?対象事件から手続き、民事訴訟との違いまで解説

従業員の横領や取引先からの詐欺など、犯罪被害に遭われた企業にとって、加害者への損害賠償請求は重要な課題です。その選択肢の一つとして、刑事裁判に付随して賠償を求める「損害賠償命令制度」がありますが、利用できるケースは限られています。この記事では、損害賠償命令制度の基本的な仕組みや対象となる事件、通常の民事訴訟との違い、具体的な手続きの流れについて、メリット・デメリットとあわせて詳しく解説します。
損害賠償命令制度とは?刑事裁判に付随する手続きの概要
制度の目的と犯罪被害者の負担軽減
損害賠償命令制度は、刑事事件の被害者が受けた損害を、簡易かつ迅速に回復させることを目的に創設された制度です。従来、被害者が加害者から賠償金を受け取るためには、刑事裁判とは別に民事訴訟を提起する必要があり、被害者には大きな負担がかかっていました。
- 被害者が自ら証拠を収集し、加害者の不法行為をゼロから立証する必要があった。
- 証拠集めや訴訟対応にかかる経済的・時間的・精神的な負担が非常に大きかった。
本制度は、刑事裁判の結果を民事上の賠償請求に直接活用する仕組みを導入することで、これらの負担を大幅に軽減するものです。刑事事件を担当した裁判所が引き続き賠償請求も審理するため、被害者の労力を最小限に抑え、速やかな救済を実現することを目的としています。
刑事裁判の記録を利用する仕組み
本制度の最大の特徴は、刑事裁判で収集された証拠資料や事実認定の結果を、そのまま賠償請求の審理で利用できる点にあります。通常の民事訴訟では、原告(被害者)が証拠を自ら集めなければなりませんが、本制度では裁判所が職権で刑事記録を取り調べます。
これにより、被害者は加害者の行為を証明するための新たな立証活動を行う必要がほとんどなくなります。刑事裁判で認定された事実が、そのまま損害賠償義務の根拠となるため、被害者の主張・立証のハードルが劇的に下がり、より確実に賠償額を確定させることが可能になります。
通常の民事訴訟との基本的な相違点
損害賠償命令制度は、被害者の保護と紛争の早期解決に特化した手続きであり、通常の民事訴訟とはいくつかの重要な違いがあります。
| 項目 | 損害賠償命令制度 | 通常の民事訴訟 |
|---|---|---|
| 審理の形式 | 審尋(原則非公開) | 口頭弁論(原則公開) |
| 審理の回数 | 原則4回以内 | 制限なし |
| 解決までの期間 | 刑事裁判終結後、数ヶ月程度 | 半年~1年以上かかることも多い |
| 申立手数料 | 請求額にかかわらず一律2,000円 | 請求額(訴額)に応じて高額になる |
| 申立先 | 事件が係属する地方裁判所 | 請求額や内容に応じた裁判所 |
このように、本制度は被害者が加害者と直接対面する心理的負担を避けつつ、低コストかつ迅速に手続きを進められるよう設計されています。
損害賠償命令制度の対象となる事件(犯罪)
対象となる特定の犯罪類型
損害賠償命令制度を利用できる犯罪は、法律で特定の類型に限定されています。主に、被害者の身体や生命、自由といった根源的な権利を侵害する、故意による重大な犯罪が対象です。
- 殺人、傷害など故意に人を死傷させた罪(未遂罪を含む)
- 不同意わいせつ、不同意性交等の罪
- 逮捕・監禁の罪
- 未成年者略取・誘拐、人身売買の罪
- 上記犯罪に付随して人を死傷させた罪
これらの犯罪は、事実関係が刑事裁判で明確になりやすく、被害者の迅速な救済が特に必要とされる類型です。
対象外となる事件の具体例
被害が重大であっても、本制度の対象から外れる犯罪も少なくありません。迅速な審理になじまない複雑な事件や、財産的な被害が中心の事件は、原則として対象外となります。
- 自動車運転致死傷罪などの過失犯(過失割合の判断が複雑なため)
- 人が負傷するに至らなかった暴行罪
- 窃盗罪、器物損壊罪などの財産犯
- 詐欺罪、業務上横領罪などの知能犯
これらの事件で賠償を求める場合は、従来通り、別途民事訴訟を提起するか、当事者間で示談交渉を行う必要があります。
企業が被害に遭いやすい詐欺罪・横領罪での適用の可否
企業が被害に遭うことの多い詐欺罪や業務上横領罪は、残念ながら損害賠償命令制度の対象には含まれていません。これらの犯罪は、被害額の算定や資金の流れの特定などが複雑で、審理に時間を要することが多いためです。
したがって、従業員による横領や取引先からの詐欺被害について刑事裁判で有罪判決が出たとしても、本制度を利用して賠償を命じてもらうことはできません。被害回復のためには、別途民事訴訟を提起するか、刑事手続の過程で加害者側と示談交渉を行うことになります。
損害賠償命令制度のメリットとデメリット
メリット:申立手数料の低さと手続きの迅速性
本制度を利用する大きなメリットは、経済的負担の軽さと手続きの迅速性です。
- 低コスト: 申立手数料が請求額にかかわらず一律2,000円と低額に設定されている。
- 迅速性: 審理が原則4回以内の期日で終結するため、刑事裁判終結後、数ヶ月程度での早期解決が期待できる。
通常の民事訴訟では請求額に応じて手数料が数十万円に上るケースもあるため、低コストで手続きを開始できる点は、被害者にとって大きな利点です。
メリット:刑事事件の証拠を利用できることによる立証の容易さ
立証の負担が大幅に軽減される点も、本制度の極めて重要なメリットです。検察官が収集した膨大な刑事記録(供述調書、実況見分調書など)を裁判所が職権で取り調べるため、被害者が独自に証拠を集める必要はほとんどありません。
刑事裁判で有罪判決が出ている以上、加害者の不法行為の存在そのものが争われることは稀です。そのため、被害者は損害額の算定といった点に主張を集中させることができ、敗訴のリスクを抑えながら確実に賠償額を確定させることが可能になります。
デメリット:対象事件が限定されている点
本制度の最大のデメリットは、利用できる犯罪の種類が厳格に限定されている点です。前述の通り、殺人や傷害、性犯罪といった特定の故意犯のみが対象であり、過失犯や財産犯は対象外です。
企業が直面しやすい横領や詐欺、情報漏洩といったトラブルの多くは本制度の対象外となります。また、例えば傷害罪で起訴されても、裁判の結果、対象外である暴行罪と認定された場合には、申立てが却下されるため、すべての被害者が利用できるわけではないという限界があります。
デメリット:加害者の異議申立てにより通常の民事訴訟へ移行する可能性
損害賠償命令の決定が出ても、加害者が2週間以内に異議を申し立てると、その決定は効力を失い、手続きは自動的に通常の民事訴訟へ移行します。この場合、迅速な解決というメリットが失われる可能性があります。
民事訴訟へ移行すると、原則4回以内という審理回数の制限はなくなり、申立人は通常の民事訴訟で定められた手数料との差額分を追納しなければなりません。加害者が時間稼ぎなどを目的に異議を申し立てるケースも少なくなく、このリスクは事前に理解しておく必要があります。
制度利用を判断する際の社内検討ポイント
企業が本制度の利用を検討する際には、以下の点を総合的に評価し、慎重に判断することが重要です。
- 対象犯罪への該当性: 被害を受けた犯罪が、制度の対象類型に該当するかどうか。
- 加害者の資力: 加害者に賠償金を支払う資産や収入があるか。債務名義を得ても回収できなければ意味がない。
- 情報開示のリスク: 審理の過程で、自社の内部情報などが加害者に開示されるリスクはないか。
- 費用対効果: 賠償金を得る実利と、手続きにかかる弁護士費用などのコストのバランス。
弁護士などの専門家と相談し、経済的な合理性も踏まえて、最適な手段を選択することが求められます。
申立てから決定までの手続きの流れ
申立ての時期と申立先の裁判所
損害賠償命令の申立てには、時期と場所に関して厳格なルールがあります。
- 申立期間: 刑事事件の起訴後から、第一審の弁論が終結するまでの間。
- 申立先: その刑事事件が係属している地方裁判所。
刑事裁判の判決言い渡し後では申立てができないため、制度利用を検討する場合は、起訴後なるべく早い段階で準備を進める必要があります。
審理:原則4回以内の期日で終了
刑事裁判で有罪判決が言い渡されると、損害賠償命令の審理が開始されます。審理は迅速に進められるよう、以下の流れで進行します。
- 刑事裁判を担当した裁判官が、職権で刑事事件の記録を取り調べる。
- 被害者(申立人)と加害者(相手方)が、損害の有無や金額について主張・立証を行う。
- 審理期日は原則として4回以内で、おおむね1ヶ月に1回のペースで開かれる。
- 数ヶ月程度で審理が終結し、裁判所が決定を下す。
もし事案が複雑で4回以内に審理を終えることが困難だと裁判所が判断した場合、手続きは通常の民事訴訟へ移行することもあります。
決定:損害賠償命令の発令
すべての審理が終結すると、裁判所は損害賠償命令の決定を下します。これは民事訴訟の判決に相当するもので、加害者に対して一定額の支払いを命じる内容となります。
この決定は、当事者からの異議申立てがなければ、確定判決と同一の効力を持ちます。また、裁判所の判断で仮執行宣言が付されることもあり、その場合は決定が確定する前でも強制執行の手続きを開始することが可能となり、賠償金回収の実効性が高まります。
損害賠償命令の決定後の対応
決定に対する不服申立て(異議)と民事訴訟への移行
損害賠償命令の決定書が送達されてから2週間以内に、加害者から適法な異議申立てがなければ、決定は確定します。しかし、加害者が決定内容に不服を申し立てた場合、その決定は効力を失い、手続きは自動的に通常の民事訴訟へと移行します。
移行後は地方裁判所の民事部で改めて審理が行われ、審理回数の制限などもなくなります。ただし、刑事記録やそれまでの主張内容は引き継がれるため、被害者側が有利な状況であることに変わりはありません。
賠償金が支払われない場合の強制執行手続き
損害賠償命令が確定した、あるいは仮執行宣言が付されたにもかかわらず、加害者が支払いに応じない場合は、強制執行の手続きにより賠償金を回収します。確定した決定書が「債務名義」となり、これに基づいて加害者の財産を差し押さえることが可能です。
具体的には、加害者の給与、預金、不動産などを差し押さえます。ただし、強制執行には別途費用がかかる上、加害者に差し押さえるべき財産がなければ、現実にお金を回収することはできません。そのため、制度利用の初期段階から加害者の資力を見極めておくことが重要です。
損害賠償命令制度に関するよくある質問
損害賠償命令の申立てに費用はかかりますか?
申立てには、以下の費用が必要となります。
- 申立手数料: 請求する賠償額にかかわらず一律2,000円の収入印紙。
- 郵便切手代: 書類の送達に使用する費用として数千円程度を裁判所に予納。
通常の民事訴訟と比較して、初期費用を大幅に抑えることができます。ただし、加害者から異議が出されて民事訴訟に移行した場合は、差額の手数料を追納する必要があります。
手続きは弁護士に依頼する必要がありますか?
法律上、本人だけで手続きを進めることは可能ですが、実務的には弁護士に依頼することを強くお勧めします。専門家によるサポートが有効な理由は以下の通りです。
- 申立てのタイミングや申立書の記載内容に専門的な判断が必要となるため。
- 損害額の算定や法的な主張の組み立てに専門知識が不可欠なため。
- 加害者から異議が出され、民事訴訟に移行した場合にスムーズに対応できるため。
法テラスの民事法律扶助などを利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらえる場合もあります。
刑事裁判の判決が出る前に申立てできますか?
はい、申立ては刑事裁判の判決が出る前に行う必要があります。申立期間は、刑事事件が起訴された後から、第一審の口頭弁論が終結するまでと定められています。判決言い渡し後にこの制度を利用することはできないため、刑事裁判の進行状況を注視し、期限を逃さないようにすることが重要です。
加害者が複数いる場合、申立てはどうなりますか?
刑事事件の被告人が複数いる場合、それぞれの被告人に対して個別に損害賠償命令を申し立てることができます。その際の注意点は以下の通りです。
- 原則として、各被告人に対して個別に申し立てを行う。
- 相手方とできるのは、あくまでその刑事裁判の被告人に限られる。
- 起訴されていない共犯者や加害者の雇用主など、被告人以外の者には別途民事訴訟を提起する必要がある。
損害賠償命令の決定に時効はありますか?
はい、あります。損害賠償命令の決定が確定すると、その賠償請求権(債権)の消滅時効期間は10年となります。これは、通常の不法行為に基づく損害賠償請求権の時効(損害及び加害者を知った時から3年または5年)よりも長く設定されています。10年が経過する前に強制執行などの手続きを行えば、時効の進行を中断させることができます。
損害賠償命令の手続き内で和解はできますか?
はい、審理の過程で裁判所から和解が勧められることもあり、当事者双方が合意すれば和解が成立します。和解が成立し、その内容が調書に記載されると、確定判決と同一の効力を持ちます。
加害者に支払い能力や意思がある場合には、分割払いを認めるなど柔軟な条件で和解することにより、訴訟を長引かせることなく、早期かつ確実な被害回復を実現できる可能性があります。
まとめ:損害賠償命令制度を正しく理解し、最適な被害回復を目指すために
本記事では、犯罪被害者の負担を軽減し、迅速な被害回復を目指す損害賠償命令制度について解説しました。この制度は、刑事裁判の記録を活用することで立証負担を大幅に軽減し、低コストかつ迅速に手続きを進められる点が大きなメリットです。しかし、対象となる犯罪が殺人や傷害罪といった特定の故意犯に限定されており、企業が被害に遭いやすい詐欺罪や横領罪は対象外である点に注意が必要です。また、加害者に資力がない場合や、異議申立てにより通常訴訟へ移行するリスクも存在します。制度の利用を検討する際は、これらのメリット・デメリットを総合的に評価し、弁護士などの専門家と相談の上で、自社の状況に最適な手段を選択することが重要です。