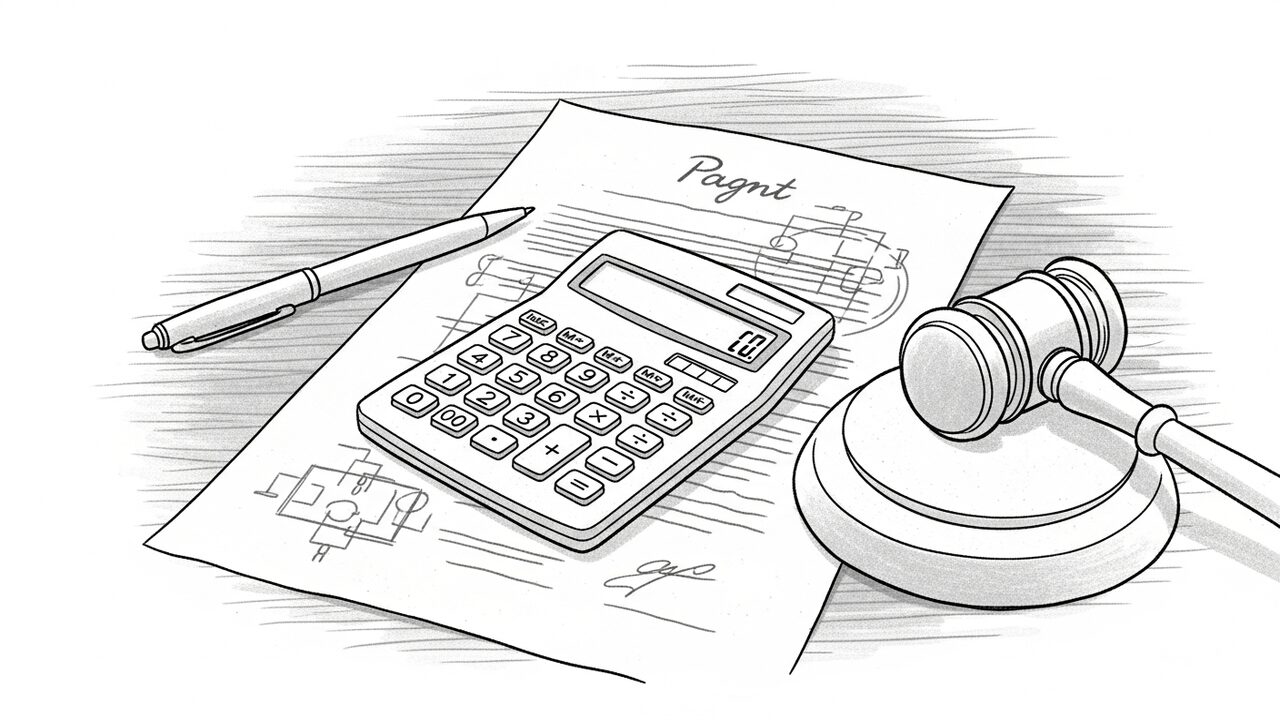民事裁判で敗訴した場合の費用負担|相手の弁護士費用は支払う必要があるか解説

民事裁判の当事者となった企業にとって、敗訴した場合の金銭的リスクを正確に把握することは、経営判断や財務計画における重要な課題です。特に、高額になりがちな弁護士費用を相手方に対して支払う義務があるのか否かは、最終的な負担総額を左右する極めて重要な論点となります。この記事では、日本の民事訴訟における費用負担の二大原則を基に、敗訴者が実際に負担する費用の内訳、例外的に相手方の弁護士費用を支払うケース、そして費用を支払えない場合のリスクまでを網羅的に解説します。
民事裁判における費用負担の大原則
原則①「訴訟費用」は敗訴者が負担する
日本の民事裁判では、裁判手続きに直接要する費用を「訴訟費用」と呼びます。この訴訟費用は、民事訴訟法第61条に基づき、原則として裁判に負けた側(敗訴者)が全額を負担します。これを「敗訴者負担の原則」といい、勝訴した当事者の経済的負担を軽減し、正当な権利の主張を後押しすることを目的としています。
具体的に訴訟費用に含まれるのは、裁判所に納める手数料や関係者への書類送達費用など、手続き遂行のための実費です。判決の主文で「訴訟費用は被告(または原告)の負担とする」といった形で言い渡され、敗訴者は自身が支出した費用だけでなく、相手方が立て替えた費用も最終的に支払う義務を負います。
- 訴状に貼付する収入印紙代(訴え提起手数料)
- 書類送達のための郵便料(予納郵券代)
- 証人を呼んだ場合の日当や旅費
ただし、勝訴した側でも、不必要に審理を遅らせる行為をした場合などには、その行為によって生じた費用を負担させられることがあります(民事訴訟法第62条、第63条)。なお、訴訟費用はあくまで裁判手続き上の実費であり、後述する弁護士費用とは明確に区別されます。また、判決が出ただけで自動的に返金されるわけではなく、費用を回収するためには別途「訴訟費用額確定処分」という手続きが必要です。
原則②「弁護士費用」は各自が負担する
訴訟にかかる費用の中で大きな割合を占める弁護士費用ですが、これは訴訟費用とは異なり、勝訴・敗訴にかかわらず各自が自分で依頼した弁護士の費用を負担するのが日本の法制度における大原則です。これを「各自負担の原則」と呼びます。
この原則が採用されている背景には、日本では弁護士を代理人に立てることが義務付けられていない(弁護士強制主義ではない)点が挙げられます。当事者本人が訴訟を行う「本人訴訟」も認められているため、弁護士に依頼するかどうかは当事者の選択に委ねられており、その費用も依頼者自身が負担すべきと考えられています。
もし弁護士費用を敗訴者負担にすると、高額な相手方の弁護士費用を支払うリスクを恐れ、正当な権利を持つ市民や中小企業が訴訟をためらってしまう「萎縮効果」が懸念されます。特に大企業などを相手取る訴訟では、このデメリットが顕著になると考えられています。
したがって、裁判に勝訴しても、原則として自身が支払った着手金や報酬金を相手方に全額請求することはできません。ただし、例外として不法行為に基づく損害賠償請求など、特定のケースでは弁護士費用の一部を損害として相手に請求することが認められています。
敗訴時に負担する費用の種類と内訳
訴訟費用に含まれる具体的な項目(印紙代・郵券代など)
訴訟費用として相手方に請求できる項目は、「民事訴訟費用等に関する法律」によって細かく定められています。これを列挙主義といい、法律に規定のない費用は請求できません。主な項目は以下の通りです。
- 訴え提起手数料:訴状に貼り付ける収入印紙代。請求額(訴額)に応じて変動します。
- 郵便料:裁判所が書類を送達するために使用する郵便切手代。実費が精算されます。
- 旅費・宿泊料:当事者、証人、鑑定人等が遠方の裁判所へ出頭した場合にかかる交通費や宿泊費。
- 証人・鑑定人等の費用:証人尋問や鑑定手続きを行った場合の日当、旅費、鑑定料など。
- 記録の謄写費用:裁判所の記録をコピーする際にかかる費用。
これらの費用は、判決後に「訴訟費用額確定処分」という手続きを経て、具体的な支払額が法的に確定します。訴訟が長期化し、出頭回数や証拠調べが増えると、これらの費用の総額も大きくなるため注意が必要です。
自身が支払う弁護士費用の内訳(着手金・報酬金など)
弁護士に依頼する際の費用は、個別の委任契約によって定められ、主に以下の要素で構成されます。現在は旧報酬基準が廃止され、各法律事務所が自由に料金を設定しているため、依頼前の見積もり確認が不可欠です。
- 着手金:事件を依頼した段階で支払う費用。結果にかかわらず原則として返還されません。
- 報酬金:事件終了時に、得られた経済的利益に応じて支払う成功報酬。敗訴した場合は発生しないのが一般的です。
- 実費:収入印紙代、郵便切手代、交通費、コピー代など、手続きを進める上で実際にかかった費用。
- 日当:弁護士が裁判所への出廷などで事務所外の活動により拘束される場合に発生する費用。
- タイムチャージ:弁護士が業務に費やした時間に応じて計算される費用。特に企業法務で用いられます。
敗訴した場合、報酬金は不要となることが多いですが、すでに支払った着手金は戻ってこないため、これがそのまま損失となります。
【具体例】敗訴した場合の費用総額シミュレーション
負担費用の計算式:訴訟費用+自己の弁護士費用
裁判で全面的に敗訴した場合、負担する費用の総額は、「相手方が立て替えた訴訟費用」と「自身が依頼した弁護士に支払う費用」の合計となります。
具体的には、相手方が裁判所に納めた収入印紙代や郵便料などの実費を全額支払う義務が生じます。それに加え、自身が弁護士に支払った着手金や、裁判の過程で発生した日当・実費も自己負担となります。成功報酬である報酬金は発生しないのが一般的ですが、すでに支払った着手金は返還されないため、大きな経済的負担となります。
結果として、勝訴側は立て替えた訴訟費用を相手方から回収できますが、敗訴側は二重の費用負担(相手の訴訟費用+自分の弁護士費用)を強いられることになります。
請求額に応じた訴訟費用(印紙代)の目安
訴訟費用の中心となる収入印紙代(訴え提起手数料)は、請求する金額である「訴額」に応じて法律で定められています。訴額が大きくなるほど印紙代も高額になります。
| 訴額(請求額) | 印紙代 |
|---|---|
| 100万円まで | 1万円(例:訴額100万円なら1万円) |
| 500万円まで | 100万円超の部分は100万円ごとに5,000円加算(例:訴額300万円なら2万円) |
| 1,000万円まで | 500万円超の部分は50万円ごとに2,000円加算(例:訴額1,000万円なら4万円) |
| 1億円まで | 1,000万円超の部分は100万円ごとに3,000円加算(例:訴額5,000万円なら16万円) |
この金額は第一審のものであり、控訴審では1.5倍、上告審では2倍の印紙代が必要となります。敗訴した場合は、相手方が支払ったこれらの印紙代を負担することになるため、訴額が大きいほどリスクも増大します。
例外的に相手方の弁護士費用を負担するケース
不法行為に基づく損害賠償請求の場合
弁護士費用は各自負担が原則ですが、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償請求の裁判では例外的な扱いがなされます。不法行為とは、故意または過失により他人の権利を違法に侵害する行為のことで、交通事故や名誉毀損などが典型例です。
これらの事件では、被害者が損害を回復するために弁護士に依頼せざるを得なかった状況を考慮し、弁護士費用も損害の一部と認められるのが実務上の通例です。ただし、実際に支払った全額ではなく、判決で認められた損害賠償額の10%程度を弁護士費用相当額として上乗せして支払いを命じるのが一般的です。
例えば、1,000万円の損害賠償が認められた場合、その1割にあたる100万円が弁護士費用として加算され、合計1,100万円の支払いが命じられることになります。この扱いは、契約違反である債務不履行に基づく請求では原則として適用されません。
訴えの提起自体が不法行為とみなされる特殊な場合
訴訟を起こす権利は憲法で保障されていますが、その権利を濫用し、嫌がらせ目的や不当な利益を得る目的で、法的根拠が全くないにもかかわらず提訴する行為は「不当提訴」として、それ自体が不法行為とみなされることがあります。
このような特殊なケースで訴えられた側は、応訴のためにやむなく支出した弁護士費用を損害として、提訴者に請求できます。この場合、通常の不法行為のように損害額の1割程度に限定されず、実際に支出した弁護士費用の一部または相当額が賠償の対象となる可能性があります。
裁判所は、裁判を受ける権利を不当に制約しないよう、不当提訴の認定には極めて慎重ですが、訴訟制度の悪用と判断されれば、提訴者は敗訴するだけでなく、相手方の弁護士費用全額を負担するという深刻なリスクを負うことになります。
判決で命じられた費用を支払えない場合のリスク
財産の差し押さえ(強制執行)を受ける可能性
判決で費用や賠償金の支払いが命じられたにもかかわらず、支払いを怠った場合、勝訴した側(債権者)は裁判所に申し立て、強制執行の手続きを取ることができます。これにより、敗訴者(債務者)の財産が強制的に差し押さえられ、債権の回収に充てられます。
- 預貯金:銀行口座が凍結され、残高が回収されます。
- 給与:勤務先に裁判所から通知が届き、原則として手取り額の4分の1が毎月差し押さえられます。
- 不動産:所有する土地や建物が競売にかけられ、売却代金が支払いに充てられます。
- 動産:自動車、機械設備、貴金属なども対象となります。
- 売掛金:法人の場合、取引先に対する売掛債権も差し押さえの対象です。
強制執行が始まると、自身の意思で止めることは困難であり、職場や取引先に事情が知られるなど、社会的な信用も大きく損なわれます。支払いが困難な場合は、放置せずに弁護士に相談し、分割払いの交渉や法的な債務整理を検討する必要があります。
敗訴に備えた引当金の計上と会計処理の留意点
企業が訴訟を提起された場合、将来の敗訴による支出に備え、会計上の処理が必要になることがあります。敗訴の可能性が高く、かつ賠償額などを合理的に見積もることができる場合には、「訴訟損失引当金」を計上し、貸借対照表に負債として表示するとともに、損益計算書に費用として計上する必要があります。
これにより、企業の財政状態を正確に利害関係者に示すことができます。ただし、税務上は、原則として判決が確定するなどして債務が法的に確定した時点ではじめて損金として認められる(債務確定主義)ため、会計上は費用計上できても、税務上は損金不算入となる点に注意が必要です。
民事裁判の費用に関するよくある質問
裁判が和解で終了した場合、費用負担はどうなりますか?
裁判の途中で話し合いにより和解が成立した場合、訴訟費用の負担は判決のように裁判所が決定するのではなく、当事者間の合意によって自由に定められます。
実務上は、お互いに譲歩して紛争を解決するという和解の性質から、「各自が支出した費用は、それぞれが負担する」と取り決めるのが最も一般的です。この場合、和解条項に「訴訟費用は各自の負担とする」という一文が盛り込まれ、相手方に費用を請求することも、相手方から請求されることもありません。
一部敗訴の場合、費用はどのように分担されますか?
原告の請求が一部だけ認められ、残りが棄却された場合(一部勝訴・一部敗訴)、訴訟費用の負担は民事訴訟法第64条に基づき、裁判所の裁量によって分担割合が決定されます。
一般的には、請求総額のうち認められなかった金額(敗訴部分)の割合に応じて按分されます。例えば、1,000万円を請求して400万円の支払いが認められた場合、請求の6割が棄却されたことになるため、「訴訟費用の10分の6を原告の負担とし、その余を被告の負担とする」といった形で命じられるのが通例です。
訴訟費用の金額はいつ、どのように確定するのですか?
判決の主文では「訴訟費用は被告の負担とする」のように負担割合が示されるだけで、具体的な金額は明記されません。費用の金額は、判決が確定した後に、勝訴者が第一審の裁判所に対して「訴訟費用額確定処分」の申立てを行うことによって、はじめて法的に確定します。
この手続きを経なければ、相手方に具体的な金額を請求したり、強制執行を行ったりすることはできません。和解で「各自負担」とした場合は、この手続きは不要です。
訴訟費用額確定処分とは?申立てから支払いまでの流れ
訴訟費用額確定処分は、判決で定められた負担割合を、具体的な金額に換算するための法的な手続きです。手続きの流れは以下の通りです。
- 勝訴者が、支出した印紙代や郵便料などをまとめた費用計算書を作成し、第一審の裁判所書記官に申し立てます。
- 申立人は、申立書類の写しを相手方にも送付します。
- 裁判所書記官は、相手方に対し、計算内容への意見を述べる機会を与えます。
- 相手方の意見も踏まえて、書記官が最終的な費用額を算定し、「決定」という形で双方に通知します。
- この決定が確定すると、判決と同様に強制執行が可能な「債務名義」としての効力を持ちます。
- 相手方が任意に支払わない場合、勝訴者はこの決定書に基づき、相手方の財産を差し押さえることができます。
まとめ:敗訴時の費用負担は「訴訟費用」と「弁護士費用」の区別が鍵
民事裁判で敗訴した場合の費用負担を理解する上で最も重要なのは、「訴訟費用」と「弁護士費用」を明確に区別することです。裁判手続きの実費である訴訟費用は敗訴者が相手方の分まで負担しますが、弁護士費用は勝敗にかかわらず各自が負担するのが日本の法制度における大原則となります。結果として、敗訴者は相手方が立て替えた訴訟費用と、自身が依頼した弁護士の着手金などを二重に負担する構造を理解しておく必要があります。ただし、不法行為に基づく損害賠償請求のように、例外的に相手方の弁護士費用の一部を損害として支払う義務が生じるケースも存在します。訴訟の見通しを立てる際は、これらの原則と例外を正確に把握し、潜在的な財務リスクを経営判断に反映させることが極めて重要です。