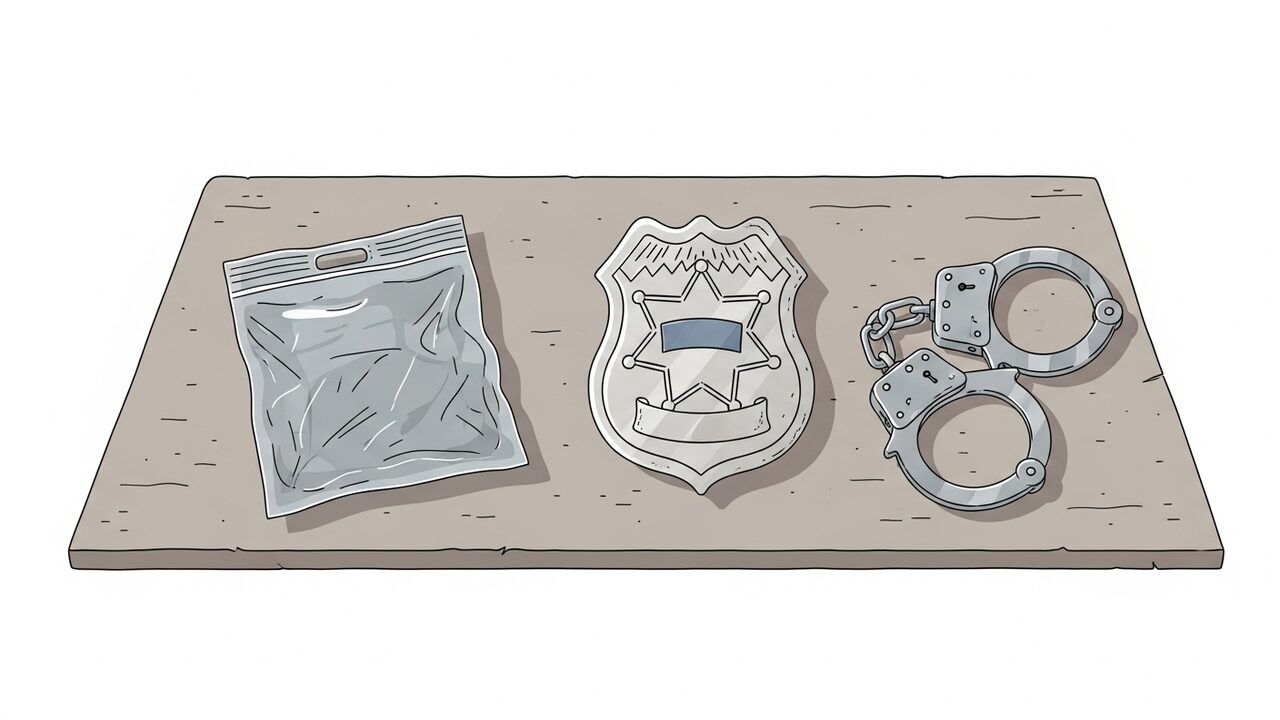裁判で負けたら費用は誰が負担?訴訟費用と弁護士費用の原則を解説

訴訟を検討する上で、敗訴時の費用負担がどの程度になるかは、経営判断を左右する重要な論点です。裁判で発生する費用には大きく分けて2種類あり、誰が負担するかの原則を知らなければ、たとえ勝訴しても想定外の出費で「費用倒れ」に陥るリスクさえあります。この記事では、裁判で負けた場合に誰がどのような費用を負担するのか、その基本原則と例外、そして勝訴後に費用を回収する具体的な手続きまでを解説します。
裁判で発生する2種類の費用
訴訟費用の内訳と目安
訴訟費用とは、裁判所を利用するために法律で定められた実費のことであり、主に申立手数料(印紙代)や郵便料などで構成されます。裁判手続きを進めるにあたり、当事者はこれらの公的な費用を負担する必要があります。
訴訟費用の総額は、請求額の大きさや事案の複雑さによって数万円から数百万円に及ぶこともあり、提訴を検討する際には事前に概算を把握しておくことが重要です。
- 申立手数料(印紙代): 訴えを提起する際に納付する手数料です。訴訟の目的の価額(請求額)に応じて算出され、例えば請求額100万円なら1万円、1,000万円なら5万円と、請求額が大きくなるほど高くなります。
- 郵便切手代(予納郵券): 裁判所が被告へ訴状や呼出状といった書類を送達するために使う費用です。当事者の人数などによって変動しますが、当事者が各1名の場合は6,000円程度をあらかじめ納めるのが一般的です。
- 証人尋問等の費用: 証人や鑑定人が裁判所に出廷する際の日当、旅費、宿泊料など、証拠調べのために必要となる実費です。
- 資格証明書の取得費用: 相手方(被告)が法人の場合に、その代表者の資格を証明する書面を取得するための費用も訴訟費用に含まれます。
弁護士費用の内訳と目安
弁護士費用は、民事訴訟のような専門的な手続きを法律の専門家である弁護士に依頼するための報酬です。これは裁判所に納める実費である訴訟費用とは全く別の費用であり、依頼する法律事務所との契約に基づいて発生します。
弁護士費用は現在自由化されているため、事務所ごとに料金体系が異なります。依頼前には必ず見積もりを取り、契約内容を十分に確認することが不可欠です。
- 法律相談料: 弁護士に事件を正式に依頼する前に、法律相談を行う際に支払う費用です。1時間あたり1万円程度が目安です。
- 着手金: 事件を依頼した段階で支払う初期費用です。事件の結果(勝敗)にかかわらず発生し、原則として返還されません。請求額300万円以下の場合は、その8%程度が目安とされています。
- 報酬金: 事件が終了した際に、勝訴や和解によって得られた経済的利益に応じて支払う成功報酬です。完全に敗訴した場合は発生しません。獲得した経済的利益が300万円以下の場合は、その16%程度が目安です。
- 日当: 弁護士が裁判所への出廷や遠方への出張など、事務所外での活動に時間を要した場合に発生する費用です。半日の出廷で3万円から5万円程度が相場となります。
- 実費: 弁護士が事件処理のために実際に支出した交通費、通信費、印紙代、コピー代などです。
- 時間制報酬(タイムチャージ): 企業の法律顧問など、稼働時間に応じて費用を計算する方式です。弁護士の経験や専門性に応じ、1時間あたり数万円で設定されます。
訴訟関連費用は損金にできる?会計・税務上の基本
法人が支出した訴訟関連費用は、その目的や性質によって会計・税務上の取り扱い、特に損金に算入できるタイミングが異なります。これは、税法上、費用は原則としてその支払債務が確定した事業年度に損金として計上するという「債務確定主義」が適用されるためです。
| 費用の種類 | 損金算入のタイミング・扱い |
|---|---|
| 弁護士への着手金 | 企業の防衛費用としての性格を持ち、原則として役務提供を受けた事業年度に損金算入が可能です。 |
| 弁護士への成功報酬金 | 判決や和解で支払債務が確定した事業年度に損金として算入します。 |
| 資産の所有権を争う費用 | 固定資産の所有権を巡る裁判費用などは、その資産の取得価額に算入する必要があり、損金にはなりません。 |
このように、訴訟費用等の税務処理は事案の内容に大きく左右されるため、個別の判断が求められます。
費用負担の基本原則
原則1:訴訟費用は「敗訴者負担」
裁判所に納付する印紙代や郵便切手代などの訴訟費用は、原則として敗訴した当事者が全額を負担します。これは、民事訴訟法に定められた大原則です(民事訴訟法第61条)。
この原則は、不当な請求によって権利を侵害された勝訴者が、権利を回復するために立て替えた実費まで負担するのは公平ではない、という考え方に基づいています。例えば、原告が全面勝訴した場合は「訴訟費用は被告の負担とする」と判決で宣言され、原告が立て替えた費用は最終的に被告に請求できます。逆に原告が全面敗訴すれば、原告が全ての訴訟費用を負担します。
ただし、勝訴した当事者が意図的に訴訟を遅延させた場合など、特定の状況では例外的に勝訴者が費用の一部を負担させられることもあります。
原則2:弁護士費用は「各自負担」
訴訟の勝敗にかかわらず、弁護士費用については、各自が依頼した弁護士の費用をそれぞれ自分で負担するのが原則です。たとえ裁判で全面勝訴しても、相手方に対して自身が支払った弁護士の着手金や報酬金を請求することは、原則としてできません。
- 弁護士への依頼は任意: 日本の法制度では、弁護士を立てずに本人で訴訟を行うことが認められており、弁護士への依頼は当事者の任意の選択とされているためです。
- 訴訟の萎縮効果の防止: もし敗訴者が相手の弁護士費用まで負担する制度になると、高額な費用負担を恐れて、正当な権利を持つ人でも提訴をためらう可能性があります。特に、資金力のない個人や中小企業にとって司法へのアクセスが妨げられる懸念があります。
この原則があるため、訴訟を検討する際は「勝訴しても弁護士費用は自己負担である」ことを前提に、費用対効果を慎重に見極める必要があります。
費用負担の例外と特殊ケース
弁護士費用を相手に請求できる場合
弁護士費用は「各自負担」が原則ですが、不法行為(交通事故、名誉毀損など)に基づく損害賠償請求のように、特定の事件類型では例外的に相手方への請求が認められることがあります。
これは、加害者の不法行為によって被害者が訴訟提起を余儀なくされた場合、そのために要した弁護士費用も加害行為と相当因果関係にある損害の一部と評価されるためです。この場合、裁判所が認めた損害額の1割程度が、弁護士費用相当額として上乗せして請求できる運用が定着しています。
- 交通事故、詐欺、暴力、名誉毀損などの不法行為に基づく損害賠償請求
- 企業の安全配慮義務違反が原因の労働災害(債務不履行だが不法行為に類似)
- 建築瑕疵や医療過誤など、不法行為またはそれに準じる債務不履行に基づく損害賠償請求
一方で、単なる貸金の返還請求や売買代金の未払いといった一般的な債務不履行のケースでは、原則通り弁護士費用の請求は認められません。
一部勝訴・敗訴の場合の費用按分
原告の請求が一部しか認められなかった場合(一部勝訴)、訴訟費用は裁判所の判断によって当事者間で按分されます。実質的に双方に勝った部分と負けた部分があるため、公平の観点から認容された割合などに応じて費用を分担させるのが合理的だからです。
例えば、原告が1,000万円を請求し、判決で400万円の支払いのみが命じられた場合、裁判所は「訴訟費用はこれを10分し、その6を原告の負担とし、その4を被告の負担とする」といった形で、判決主文で負担割合を具体的に定めます。この割合に従って、当事者がそれぞれ立て替えた訴訟費用を最終的に精算することになります。
過大な請求を行うと、かえって自身の訴訟費用負担の割合を増やすリスクがあるため、提訴の段階で証拠に基づいた現実的な請求額を設定することが重要です。
和解で終了した場合の費用負担
裁判上の和解によって紛争が解決した場合、それまでにかかった訴訟費用は各自の負担とするのが実務上の基本です。和解は双方が譲歩し合うことで成立するため、お互いに費用の請求はしないことで、円満かつ早期の紛争解決を図ります。
通常、和解が成立する際には、和解条項に「訴訟費用は各自の負担とする」という一文が盛り込まれます。これにより、原告が納付した印紙代なども含め、それぞれが支出した分をそのまま負担して終了となります。
ただし、和解は柔軟な解決手続きであるため、当事者間の合意があれば、費用の負担割合を別途定めることも可能です。また、実務上は、被告が支払う「解決金」の金額に、原告が負担した訴訟費用相当額を実質的に上乗せして調整するといった交渉も行われます。
勝訴後の費用回収手続き
相手方に請求できる費用の範囲
勝訴判決に基づき、敗訴した相手方に請求できる費用は、法律で定められた訴訟費用に限られます。弁護士費用はここに含まれません。
請求できるのは、あくまで裁判手続きのために直接要した実費であり、支出した全額が認められるわけではなく、法律の基準に基づいて算出された金額となります。
- 申立手数料: 提訴時に納付した印紙代。
- 郵便切手代: 書類の送達に用いた郵便料金。
- 証人尋問等に要した日当・旅費: 証人や鑑定人が裁判所に出頭した際の日当や交通費、宿泊費(法定の基準内で算出)。
- 証拠調べ費用: 証人尋問に要した旅費や日当など。
- 資格証明書取得費用: 法人の代表者資格証明書などを取得した際の実費。
「訴訟費用額確定処分」の申立て
判決では費用の負担割合が示されるだけなので、相手方に具体的な金額を請求するためには、別途「訴訟費用額確定処分」という手続きを裁判所に申し立てる必要があります。
この手続きの流れは以下の通りです。
- 判決が確定した後、勝訴者が費用計算書と支出を証明する証拠書類の写しを裁判所に提出して申し立てます。
- 裁判所書記官が相手方に申立書類の副本を送付します。
- 裁判所書記官が相手方に意見を求め、相手方も支出した費用があれば計算書を提出します。
- 裁判所書記官は双方の費用を相殺計算し、最終的に一方が相手方に支払うべき金額を決定します。
- この決定書(訴訟費用額確定処分)は債務名義となり、これに基づいて強制執行(財産の差し押さえなど)が可能になります。
勝訴後の費用回収における実務上の注意点
訴訟費用額確定処分を得て請求権が確定しても、相手方に支払う資力がなければ、実際に費用を回収することはできません。手続きを進める前に、回収の実効性を見極めることが重要です。
- 相手方の支払い能力の確認: 強制執行の対象となる預貯金や不動産といった財産が相手方にあるかどうかが、回収の最大のポイントです。
- 費用倒れのリスク: 回収できる訴訟費用が少額な場合、確定処分の申立てや強制執行にかかる追加の費用が回収額を上回ってしまう「費用倒れ」に注意が必要です。
- 冷静な費用対効果の判断: 勝訴したからといって機械的に手続きを進めるのではなく、回収にかかる手間やコストと、実際に得られる経済的利益を比較検討することが求められます。
よくある質問
Q. 裁判費用が払えない場合、どうなりますか?
経済的な理由で裁判費用を支払えない場合でも、いくつかの公的な救済制度を利用することで、裁判を起こす道が開かれています。国民が裁判を受ける権利を保障するための仕組みです。
- 訴訟上の救助: 裁判所に申し立て、資力がないことを証明できれば、判決が確定するまで印紙代などの支払いが猶予される制度です。ただし、明らかに勝訴の見込みがないと判断される場合は利用できません。
- 民事法律扶助制度(法テラス): 日本司法支援センター(法テラス)が行う制度で、収入や資産が一定基準以下の場合に、弁護士費用や訴訟費用を立て替えてもらえます。立て替えられた費用は、原則として月々分割で返済していくことになります。
手元に資金がなくても、これらの制度を活用することで権利の実現を目指すことが可能です。
Q. 訴訟費用はいつ誰が立て替えるのですか?
訴訟費用は、原則として訴えを起こす原告が、提訴するタイミングでいったん全額を立て替えて裁判所に納付する必要があります。
裁判所が手続きを開始し、被告に訴状を送達するためには、まず手数料や郵便料を納めなければならないと法律で定められているからです。具体的には、訴状を提出する際に請求額に応じた収入印紙を貼り、郵便切手を予納します。
裁判の途中で証人尋問などが必要になった場合も、その証拠調べを申し出た側が都度関連費用を予納します。最終的に判決で相手方負担とされたとしても、まずは手続きを進める側が自己資金で費用を賄う必要があるため、提訴前の資金計画が重要です。
Q. 本人訴訟の場合、費用は安くなりますか?
弁護士に依頼せず、自分で裁判を行う「本人訴訟」を選択すれば、弁護士費用(着手金や報酬金)が一切かからないため、費用総額は大幅に安くなります。しかし、費用面でのメリットがある一方で、専門知識不足による大きなリスクも伴います。
| 観点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 費用面 | 弁護士費用が一切かからないため、初期費用を抑えられる。 | 敗訴した場合、本来得られたはずの経済的利益を全て失うリスクがある。 |
| 手続き・労力面 | 法的知識に基づいた書類作成や法廷対応を全て自分で行う必要がある。 | |
| 時間面 | 平日の日中に開かれる裁判期日に、毎回自分自身で出頭しなければならない。 | |
| 結果 | 主張や立証が不十分となり、本来勝訴できる事案で敗訴する可能性が高まる。 |
本人訴訟は、金銭的な負担を軽減できる反面、敗訴のリスクや時間的・精神的な負担が増大します。事案の複雑さや重要度をよく見極め、慎重に判断することが不可欠です。
まとめ:裁判の費用負担、敗訴時のリスクを正確に把握するために
裁判で発生する費用負担は、「訴訟費用は敗訴者負担」「弁護士費用は各自負担」という2つの大原則を理解することが基本です。ただし、不法行為に基づく損害賠償請求など、例外的に弁護士費用の一部を相手方に請求できるケースも存在します。訴訟を検討する際は、この原則と例外をふまえ、勝訴の見込みだけでなく、回収できる金額と自己負担する弁護士費用との費用対効果を冷静に見極めることが経営判断の軸となります。実際に訴訟に踏み切る前には、自社のケースがどの原則・例外に該当するのか、そして勝訴後に相手方から費用を回収できる見込み(相手方の資力)はどの程度あるのかを、事前に弁護士などの専門家に相談し、具体的な見通しを確認することが不可欠です。本記事で解説した内容はあくまで一般的な原則であり、個別の事案における最終的な費用負担の割合や金額は裁判所の判断によって決まるため、専門家のアドバイスを元に慎重に検討してください。