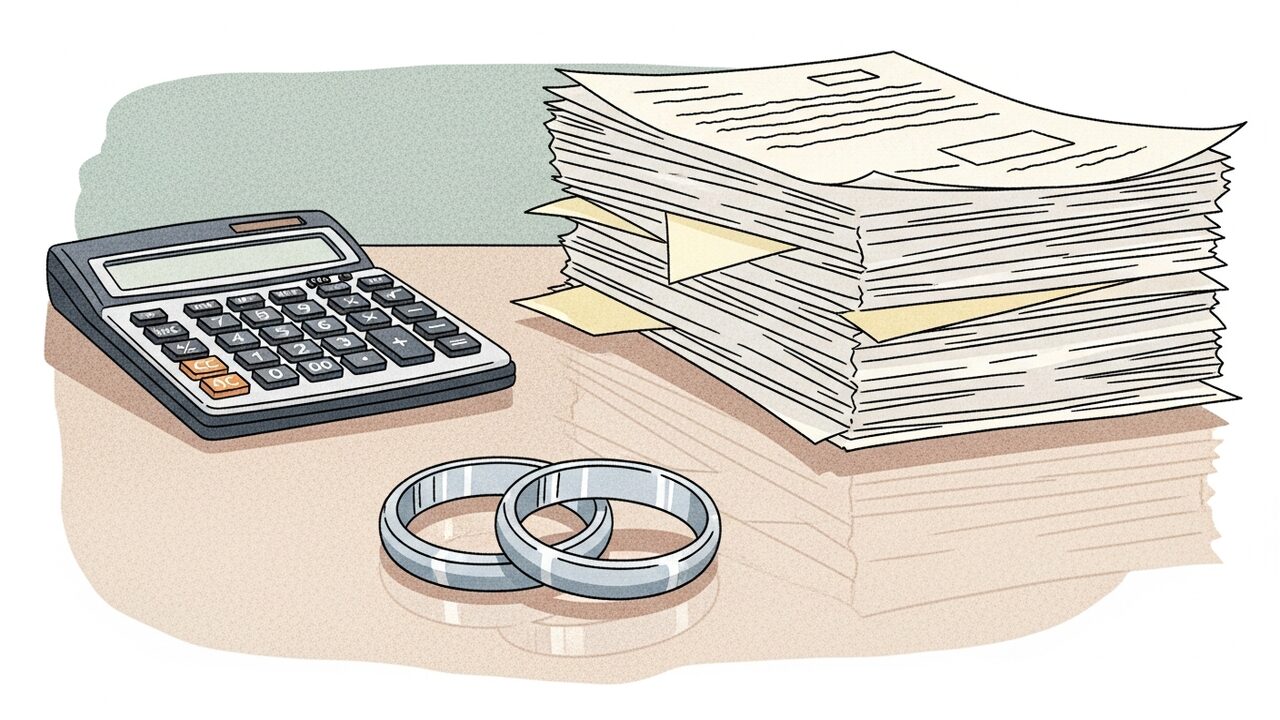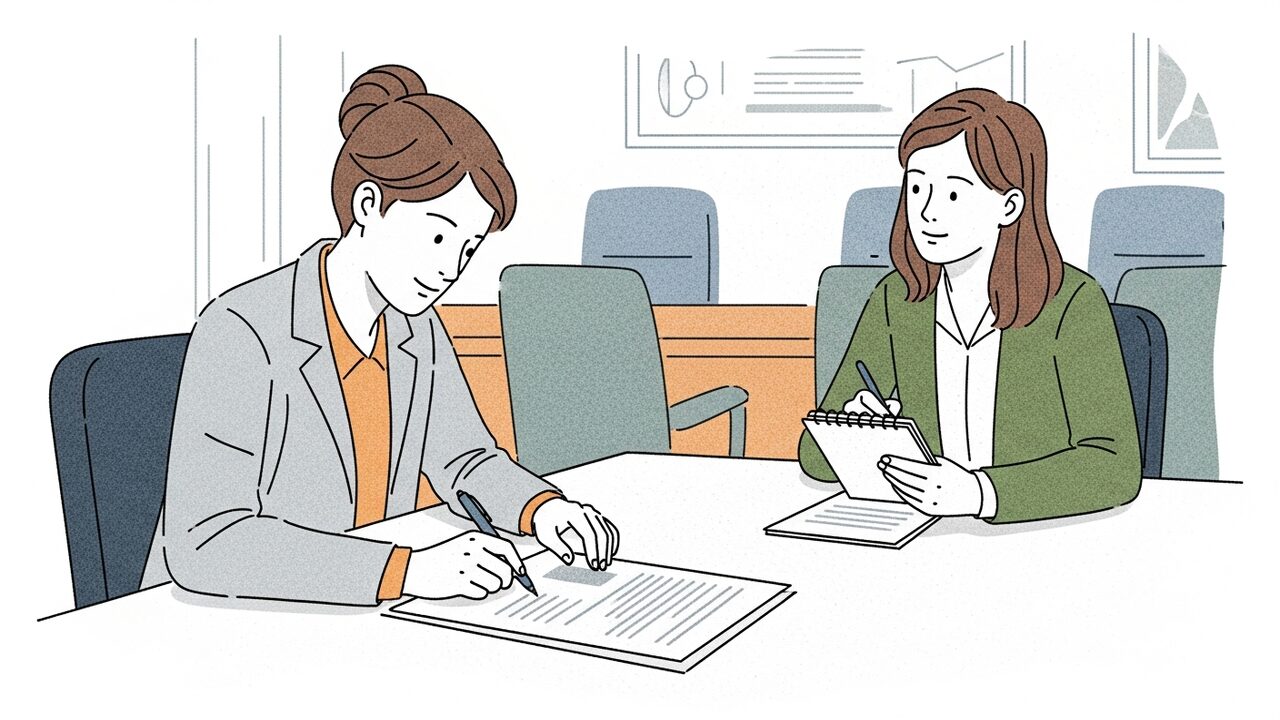繰越欠損金とは?計算方法や適用要件、税効果会計までわかりやすく解説

過去の事業年度に生じた赤字は、将来の税負担を軽減できる重要な経営資源となり得ます。この税務上の赤字、すなわち「繰越欠損金」を当期の黒字と相殺することで、法人税額を圧縮し、手元資金を確保することが可能です。しかし、制度を最大限活用するには、適用要件や正しい計算方法の理解が不可欠です。この記事では、繰越欠損金制度の基本から、具体的な計算例、申告書での確認方法、税効果会計上の処理までを網羅的に解説します。
繰越欠損金とは?制度の基本と節税の仕組み
繰越欠損金制度の概要と目的
繰越欠損金とは、法人税法上の用語で、各事業年度の所得計算において損金の額が益金の額を超えた場合に生じるマイナスの金額(税務上の赤字)を指します。法人税は事業年度ごとに課税所得を計算して納めるのが原則ですが、企業の経済活動は長期にわたるため、単年度の業績だけで税負担を判断するのは実態にそぐわない場合があります。
そこで、ある年度に生じた欠損金を翌事業年度以降に繰り越し、将来発生する所得(黒字)から控除できるようにしたのが繰越欠損金制度です。この制度は、過去の赤字と将来の黒字を相殺することで税負担を平準化し、企業の経営安定化や事業再生を支援することを目的としています。原則として、青色申告を行っている法人がこの制度の適用を受けられます。
繰越欠損金控除による具体的な節税メリット
繰越欠損金控除の最大のメリットは、将来納める法人税等の税額を直接的に減らせる点にあります。過去の欠損金を将来の所得と相殺することで課税所得が圧縮され、結果として納税額が減少します。
例えば、前期に1,000万円の欠損金があり、当期に800万円の所得が発生した場合、所得の全額を欠損金で相殺し、当期の課税所得をゼロにできます。課税所得がゼロになれば、法人税だけでなく、それに連動する他の税金の負担も軽減されます。これにより手元資金を確保し、資金繰りの改善や将来への投資に充てることが可能になります。ただし、資本金1億円超の大法人などには控除額に上限が設けられています。
- 法人税
- 地方法人税
- 法人住民税(法人税割)
- 事業税(所得割)
繰越欠損金控除を適用するための要件と期間
要件1:欠損金が発生した事業年度に青色申告書を提出している
繰越欠損金控除を受けるための大前提は、欠損金が生じた事業年度において、青色申告書で確定申告を行っていることです。青色申告は、複式簿記による記帳など一定の要件を満たした法人にのみ認められる特典です。
たとえ多額の赤字が発生しても、その年度の申告が白色申告だった場合、原則としてその欠損金を翌年度以降に繰り越すことはできません。ただし、災害によって生じた損失(災害損失欠損金)については、白色申告でも繰越が認められる例外規定があります。将来の節税メリットを逃さないためにも、創業時から青色申告の承認申請を行い、期限内に申告を済ませることが重要です。
要件2:欠損金発生後の事業年度も連続して確定申告書を提出している
第二の要件は、欠損金が発生した事業年度の翌年度以降、毎年連続して確定申告書を提出していることです。これにより、税務署は欠損金の利用状況を継続的に把握できます。
重要なのは、欠損金発生後の申告書は必ずしも青色申告書である必要はないという点です。欠損金が発生した年度さえ青色申告であれば、その後白色申告になったとしても、申告を継続している限り繰越控除の権利は維持されます。しかし、一度でも申告書の提出が途切れると、その時点で残っていた繰越欠損金は利用できなくなるため、赤字が続いていても毎期の確定申告は必ず行わなければなりません。
要件3:帳簿書類等を所定の期間保存している
第三の要件として、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類等を、定められた期間保存することが義務付けられています。これは、税務調査などで欠損金の発生根拠を証明するために必要です。
保存期間は、欠損金の繰越期間に合わせて原則10年間です(平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じた欠損金については9年間)。これらの書類が保存されていない場合、欠損金の存在を否認されるリスクがあるため、厳重な管理が求められます。
- 総勘定元帳、仕訳帳などの会計帳簿
- 貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類
- 契約書、請求書、領収書などの取引に関する証憑書類
欠損金の繰越が可能な期間(最長10年)と起算日の考え方
欠損金を繰り越せる期間は、税制改正によって変更されており、欠損金が発生した事業年度の開始日によって異なります。
| 欠損金の発生事業年度 | 繰越期間 |
|---|---|
| 平成30年4月1日以後に開始した事業年度 | 10年間 |
| 平成20年4月1日以後に開始し、平成30年3月31日までに開始した事業年度 | 9年間 |
期間の起算日は、欠損金が発生した事業年度の翌事業年度の開始日からです。例えば、3月決算法人が令和5年3月期に欠損金を生じた場合、令和6年3月期から令和15年3月期までの10年間にわたって繰越控除が可能です。この期間を過ぎると、未使用の欠損金は切り捨てられ、利用できなくなります。
繰越欠損金の申告漏れや期限切れを防ぐ社内管理のポイント
繰越欠損金を無駄なく活用するには、発生年度ごとの金額と繰越期限を正確に管理する体制が不可欠です。複数の年度にわたる欠損金がある場合、最も古い年度に発生したものから順に控除されていくルールのため、期限管理が特に重要になります。
- 法人税申告書「別表七(一)」で、発生年度ごとの残高と期限を毎年確認する。
- 顧問税理士と連携し、毎期の申告で控除漏れがないかチェックする。
- M&Aや組織再編を行う際は、欠損金の引継ぎに制限がかかる場合があるため、専門家と事前に検討する。
【具体例】繰越欠損金を用いた法人税額の計算方法
繰越欠損金控除を適用した法人税額の計算は、以下の3つのステップで行います。
ステップ1:繰越欠損金の金額を確認する(申告書別表七(一)の見方)
まず、自社で利用できる繰越欠損金がいくらあるかを確認します。この金額は、法人税申告書の一部である「別表七(一) 欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」に記載されています。
具体的には、直前期の申告書に添付された別表七(一)の「翌期繰越額」の合計欄を確認すれば、当期首時点で利用可能な欠損金の総額がわかります。
ステップ2:当期の所得金額から控除できる上限額を計算する
次に、当期の所得から控除できる欠損金の上限額を計算します。この上限額は、法人の規模によって異なります。
| 法人の区分 | 控除上限額 |
|---|---|
| 中小法人等(資本金1億円以下など) | 所得金額の100% |
| 大法人等(資本金1億円超など) | 繰越控除前の所得金額の50% |
中小法人等の場合は、繰越欠損金が十分にあれば、所得の全額を控除して課税所得をゼロにできます。一方、大法人等の場合は、所得の半分までしか控除できず、残りの所得に対しては法人税が課税されます。
ステップ3:繰越欠損金を控除して課税所得と法人税額を算出する(計算例)
最後に、ステップ2で計算した上限額の範囲内で繰越欠損金を控除し、課税所得と法人税額を算出します。ここでは、当期所得500万円、繰越欠損金800万円のケースで考えます。
- 中小法人の場合(控除上限100%)
- 控除できる金額:500万円(所得の100%)
- 課税所得:500万円(所得) - 500万円(控除額) = 0円
- 法人税額:0円(均等割などを除く)
- 翌期への繰越欠損金:800万円 - 500万円 = 300万円
- 大法人の場合(控除上限50%)
- 控除できる金額:250万円(所得500万円 × 50%)
- 課税所得:500万円(所得) - 250万円(控除額) = 250万円
- 法人税額:250万円 × 法人税率(別途計算が必要)
- 翌期への繰越欠損金:800万円 - 250万円 = 550万円
繰越欠損金に関する税効果会計の処理と仕訳例
税効果会計における繰越欠損金の取り扱いとは
税効果会計は、会計上の利益と税務上の所得のズレ(一時差異)を調整し、法人税等を適切に期間配分するための会計処理です。繰越欠損金は、将来の課税所得を減らすことで税金負担を軽減する効果があるため、この効果を「繰延税金資産」という資産として貸借対照表に計上します。
ただし、繰延税金資産を計上できるのは、将来的に課税所得が発生し、実際に欠損金を利用できるという「回収可能性」が見込まれる場合に限られます。将来の黒字転換が難しいと判断される場合は、資産として計上することはできません。
繰越欠損金発生時の仕訳例(繰延税金資産の計上)
欠損金が発生した事業年度の決算で、回収可能性があると判断された場合、将来の節税効果額を繰延税金資産として計上します。計算式は「繰越欠損金の額 × 法定実効税率」です。
【例】欠損金100万円が発生し、法定実効税率が30%の場合
- 借方:繰延税金資産 30万円
- 貸方:法人税等調整額 30万円
この仕訳により、損益計算書では「法人税等調整額」がマイナスの費用(つまり利益)として計上され、会計上の当期純損失が縮小します。
繰越欠損金利用時の仕訳例(繰延税金資産の取崩し)
翌期以降に黒字(所得)が出て、実際に繰越欠損金を利用して税負担が軽減された場合、計上していた繰延税金資産を取り崩します。
【例】翌期に所得が発生し、前期の欠損金のうち50万円を利用した場合(税率30%)
- 借方:法人税等調整額 15万円 (50万円 × 30%)
- 貸方:繰延税金資産 15万円
この仕訳により、実現した節税効果の分だけ繰延税金資産が減少し、損益計算書上の税金費用が適切に調整されます。
繰延税金資産の「回収可能性」を判断する実務上のポイント
繰延税金資産の「回収可能性」の判断は、将来の課税所得の見積もりに基づいて慎重に行う必要があります。実務指針では、過去の業績などに応じて企業を5つの分類に分け、計上できる資産額の範囲を定めています。
将来の事業計画や収益計画の合理性が、回収可能性を判断する上で極めて重要です。監査人や税理士などの専門家と協議しながら、客観的な根拠に基づいて判断することが求められます。
| 企業の分類 | 過去の業績等の状況 | 繰延税金資産の計上可否 |
|---|---|---|
| 分類1 | 過去および当期に安定して課税所得を計上 | 原則、全額計上が可能 |
| 分類2~4 | 業績が不安定、または一時的な要因で欠損を計上 | 将来の課税所得の見積額の範囲内で計上が可能 |
| 分類5 | 過去3年以上重要な欠損を計上し、翌期も重要な欠損が見込まれる | 原則、計上不可 |
繰越欠損金に関するよくある質問
繰越欠損金を利用する上でのデメリットや注意点はありますか?
繰越欠損金の利用自体に直接的な金銭デメリットはありませんが、いくつかの注意点があります。制度を正しく活用するためには、これらの点を理解しておくことが大切です。
- 青色申告の維持や帳簿保存(10年間)といった事務的な負担が発生する。
- 欠損金が多額に累積している状態は、金融機関からの融資審査で財務体質が弱いと見なされる可能性がある。
- 資本金1億円超の大法人は控除上限(所得の50%)があるため、欠損金が残っていても納税が発生する。
税務上の「欠損金」と会計上の「赤字」は同じ意味ですか?
税務上の「欠損金」と、決算書上の「赤字(当期純損失)」は、似ていますが厳密には異なる概念です。会計上の利益は「収益-費用」で計算しますが、税務上の所得は「益金-損金」で計算され、それぞれの計算ルールが異なるためです。
例えば、会計上は費用として計上される交際費や役員賞与の一部は、税務上は損金として認められない(損金不算入)ことがあります。こうした税務調整の結果、会計上は赤字でも税務上は所得がプラスになり、欠損金が発生しないケースもあります。そのため、両者の金額は必ずしも一致しません。
| 項目 | 税務上の欠損金 | 会計上の赤字(当期純損失) |
|---|---|---|
| 計算式 | 益金 - 損金 | 収益 - 費用 |
| 根拠法令等 | 法人税法 | 企業会計原則 |
| 金額が異なる要因 | 交際費の損金不算入など、税務調整項目の有無 | なし(会計ルールに基づき計算) |
期限切れで使えなくなった繰越欠損金はどうなりますか?
繰越期間(現行10年)を過ぎてしまった未使用の欠損金は、原則として切り捨てられ、その節税効果は消滅します。通常の事業活動において、期限切れの欠損金を将来の所得と相殺することはできません。
ただし、例外として、法人が解散して清算手続きに入った場合や、会社更生法の適用を受けて債務免除益が発生した場合など、特定の状況下では期限切れ欠損金を損金に算入できる特例があります。これは企業の円滑な清算や再生を支援するための措置であり、通常の経営を行っている法人には適用されません。
まとめ:繰越欠損金を正しく活用し、着実な節税と経営安定化へ
繰越欠損金は、過去の赤字を将来の利益と相殺し、法人税負担を軽減できる非常に有効な制度です。この恩恵を最大限に受けるためには、欠損金発生年度の青色申告、その後の連続申告、そして原則10年間の帳簿保存という3つの適用要件を確実に満たすことが大前提となります。特に、法人税申告書の「別表七(一)」は、利用可能な欠損金の残高と期限を管理する上で不可欠な書類であり、毎期必ず確認すべきです。まずは自社の申告書を元に現状を把握し、正確な計算と計画的な活用によって、着実な節税と経営の安定化を実現してください。