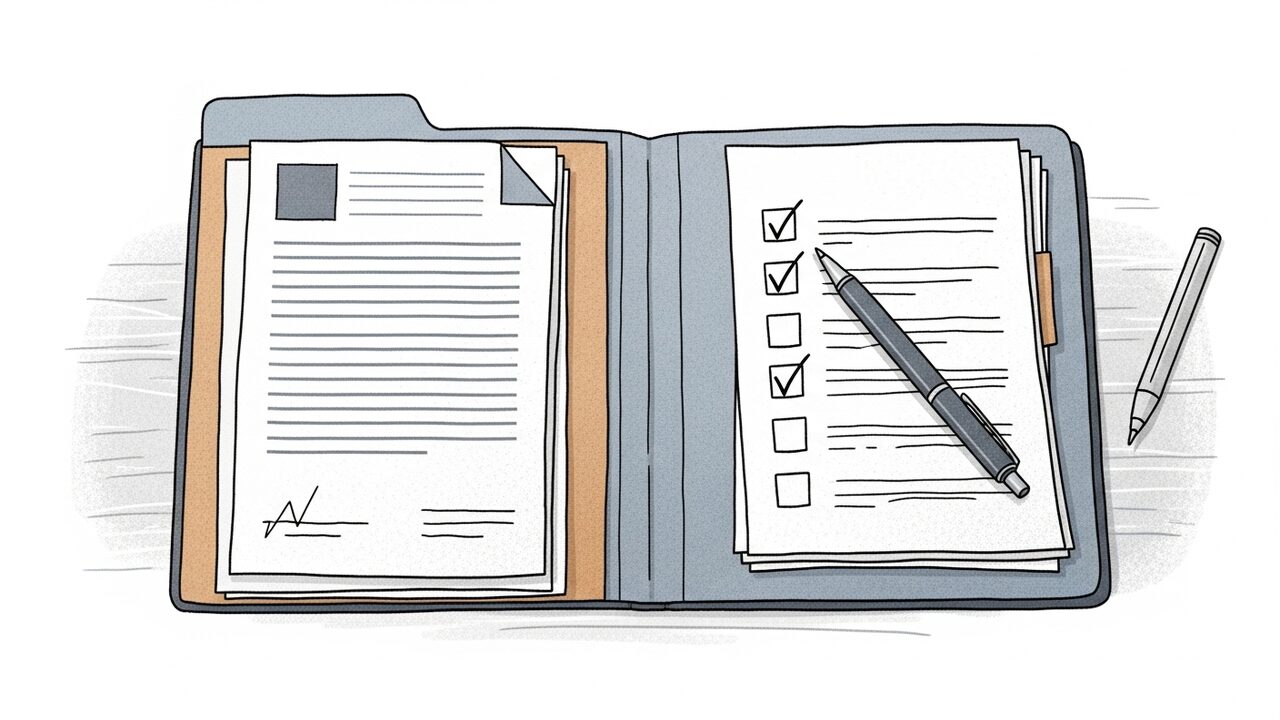日立の事業再編:リーマンショック後の危機からLumada戦略による変革までの軌跡

多くの企業が事業ポートフォリオの最適化という経営課題に直面する中、日立製作所が断行した大規模な事業再編は、重要な示唆を与えてくれます。かつて巨額の赤字に苦しんだ同社が、いかにして危機を乗り越え、グローバルな高収益企業へと変貌を遂げたのか、その戦略に関心が集まっています。この記事では、日立の事業再編について、その背景にある経営危機から「選択と集中」の具体的な手法、そして戦略的M&Aがもたらした成果までを体系的に解説します。
日立の事業再編、その歴史的背景と全体像
リーマンショックによる巨額赤字と経営危機:事業再編の出発点
日立製作所が高収益企業へ転換する契機は、2008年のリーマンショックに端を発する経営危機でした。2009年3月期連結決算では、日本の製造業として過去最大となる7,873億円の最終赤字を計上。この危機は、世界的な景気後退のみならず、日立が長年抱えていた構造的問題を露呈させました。当時の日立は、多数の上場子会社を抱えるコングロマリットであり、優良子会社の利益で本体や不採算事業の赤字を補填する収益構造でした。このため業績の悪い事業が温存されやすく、外部環境の激変によって経営基盤が大きく揺らぎました。市場からは「沈む巨艦」と評されるほど深刻な状況下で、経営陣は抜本的な改革を決断。従来の延長線上にない、ドラスティックな経営改革として、ガバナンス改革による意思決定の迅速化、不採算事業からの撤退、成長分野への経営資源集中などを断行しました。特に、グループ全体最適の視点で事業ポートフォリオを見直す方針への転換が、その後のV字回復の礎となりました。
「選択と集中」の断行:事業ポートフォリオ見直しの変遷
経営危機からの脱却のため、日立は「選択と集中」を基本方針に、事業ポートフォリオの大胆な見直しに着手しました。まず、収益性が低く、コモディティ化が進んだ事業から撤退。かつて主力だった製品でも、グローバルな価格競争で収益確保が困難なものは売却や生産中止の対象となりました。 一方で、経営資源を集中する分野として「社会イノベーション事業」を明確に定義。これは、日立が持つ制御技術(OT)と情報技術(IT)を融合させ、社会インフラ分野で高い付加価値を生み出す事業領域です。2010年代前半から、総合電機メーカーからの脱却と社会イノベーション事業へのシフトを鮮明にしました。この方針のもと、聖域なき事業の入れ替えが進められ、2009年時点で22社あった上場子会社は、完全子会社化や売却を経て最終的にゼロとなり、親子上場に起因するガバナンス不全や事業重複といった課題も解消されました。
コングロマリットからグローバルソリューション企業への転換
事業ポートフォリオの再編と並行し、日立は従来のプロダクトアウト型(製品中心)のビジネスモデルから、顧客の課題解決を起点とするマーケットイン型のソリューション企業へと転換を進めました。この変革を象徴するのが、機器から得られるデータを活用して継続的な価値を提供するデジタルソリューションです。単に製品を販売するだけでなく、運用効率化や予兆保全などのサービスを組み合わせるリカーリングビジネスの拡大を目指しました。 グローバル展開においても、単なる製品輸出から、開発・製造・販売・サービスまでを現地で一貫して行う体制へとシフト。鉄道や電力システムなどのインフラ事業では、海外の有力企業を戦略的に買収し、その顧客基盤や技術力を取り込むことで、グローバル化を加速させました。結果として海外売上収益比率は大幅に上昇し、複合企業特有の市場評価の低さ(コングロマリット・ディスカウント)を克服しつつ、各事業が連携してシナジーを生み出すグローバル企業としての地位を確立しています。
再編を支えたグループガバナンス改革と対話の文化
一連の事業再編を成功に導いたのは、実効性のあるガバナンス改革です。日立は執行と監督の分離を徹底するため、以下の改革を実行しました。
- 指名委員会等設置会社への移行
- 外国人を含む独立社外取締役の増員と役割強化
取締役会では、執行側の提案に対して社外取締役から忖度のない厳しい意見が交わされ、M&A案件が否決されるなど、緊張感のある議論が行われています。こうしたトップダウンの改革に加え、現場レベルでは、危機感を共有し、自社の強みと弱みを客観的に見つめ直すオープンな対話の文化が醸成されました。この風土が、痛みを伴う改革の実行力を高める重要な土台となりました。
事業再編を牽引する中核戦略:社会イノベーション事業とLumada
成長のエンジン「社会イノベーション事業」への経営資源集中
日立の再生と成長を牽引する中核が「社会イノベーション事業」です。これは、電力・鉄道などの社会インフラシステムに、AIやビッグデータ解析といった高度なITを組み合わせ、社会課題の解決と顧客価値の向上を同時に実現する事業コンセプトです。日立は、創業以来培ってきた現場機器を制御・運用するOT(Operational Technology)の知見と、長年のシステム開発で培ったIT(Information Technology)のノウハウを併せ持つという、世界でも稀有な強みを有しています。この強みを活かし、環境問題や都市機能の効率化といったグローバルな課題に対し、製品単体ではなくシステム全体の最適化ソリューションを提供。M&Aや研究開発投資をこの分野に集中させることで、景気変動の影響を受けやすい製品売り切り型ビジネスから、長期的かつ安定的な収益が見込めるサービス主導型のビジネスモデルへの転換を加速させています。
デジタルプラットフォーム「Lumada」を軸とした事業選別
社会イノベーション事業を推進するデジタル基盤が、2016年に始動した「Lumada(ルマーダ)」です。これは特定のソフトウェアではなく、顧客データから新たな価値を創出するためのソリューション・技術・ノウハウの総称であり、日立のDX戦略の中核を成します。事業の投資や撤退を判断する際には、その事業が「Lumadaと親和性があるか」「Lumadaの拡大に寄与するか」が重要な基準となっており、経営戦略の羅針盤としての役割も担っています。 Lumadaの最大の特徴は、顧客との「協創」を前提としている点です。顧客と課題を共有し、日立の技術群を組み合わせて解決策を共創します。そこで生まれた成功事例は「ユースケース」として蓄積・体系化され、類似の課題を持つ他の顧客へ横展開することで、スケーラブルな成長を目指しています。このサイクルにより、個別の受託開発に留まらないプラットフォームとしての収益性を高めており、Lumada事業の売上や利益は全社的な経営目標(KPI)に設定されています。
OT・IT・プロダクトの三位一体で進める事業ポートフォリオ改革
日立の事業ポートフォリオ改革における最大の差別化要因は、以下の3要素を自社グループ内で一体的に提供できる点にあります。
- OT(制御・運用技術): 社会インフラや工場の現場を動かすノウハウ
- IT(情報技術): データ活用やシステム構築を担うデジタル技術
- プロダクト: 高い信頼性を持つインフラ機器や産業用製品群
IT企業は現場の機器を持たず、重電メーカーはITを外部に依存することが多い中、日立はこの3つを垂直統合的に保有しています。事業ポートフォリオの見直しでは、この「三位一体」によるシナジーを発揮できるかが重要な判断基準となります。例えば、エレベーター事業では、製品(プロダクト)、制御技術(OT)、遠隔監視・故障予知システム(IT)を組み合わせることで高付加価値サービスを実現しています。逆に、この連携による付加価値向上が見込みにくい事業は、売却等の対象として検討され、競争優位性を確立できる領域へのリソース集中が進められています。
「Lumadaか否か」を判断する事業評価の仕組みと意思決定プロセス
日立の事業投資・撤退の意思決定は、財務指標と戦略的適合性の両面から行われます。単に黒字かどうかだけでなく、その事業がLumadaエコシステムの中でどのような役割を果たすかが重視されます。 評価軸には、資本効率を示すROIC(投下資本利益率)に加え、データ活用による拡張性、グローバル展開の可能性、社会課題解決への貢献度などが含まれます。経営会議では、各事業がLumadaの中核となり得るか、あるいはLumadaを活用して収益性を高められるかが厳しく問われます。この基準に合致しない事業は、たとえ黒字であってもポートフォリオからの切り離しが検討されるなど、全社戦略に基づいた厳格な事業評価プロセスが確立されています。
大規模な事業売却と戦略的買収の具体例
主要子会社(御三家)の売却:日立金属・日立化成・日立建機
日立の事業再編を象徴するのが、かつて「御三家」と呼ばれた主要上場子会社の売却です。これらの企業は各分野で高い技術力を有していましたが、日立本体が目指す社会イノベーション事業とのシナジーが薄く、親子上場の課題も抱えていました。日立は、各社が独立した企業として、あるいは日立グループ外の「ベストオーナー」と組む方が成長できると判断し、売却を決断しました。
| 対象会社 | 売却先・移行後の位置づけ | 時期(目安) |
|---|---|---|
| 日立化成 | 昭和電工(現:レゾナック・ホールディングス)に売却 | 2020年 |
| 日立金属 | 米投資ファンド主導のコンソーシアムに売却(現:プロテリアル) | 2022年 |
| 日立建機 | 保有株式の一部を伊藤忠商事などに譲渡し、持分法適用会社へ移行 | 2022年 |
これらの売却で得た巨額の資金は、有利子負債の削減による財務体質の改善と、後述するIT・エネルギー分野での大型買収の原資として活用されました。これは単なるリストラではなく、成長分野へのシフトを加速させるための「攻めの撤退」でした。
海外企業の大型買収(1):ABB社パワーグリッド事業の統合
事業売却で得た資金を元に、日立はグローバルでの競争力を飛躍的に高める大型買収を実行しました。その代表例が、2020年に完了したスイスの重電大手ABB社からのパワーグリッド(送配電)事業の買収です。総額約1兆円規模に達したこの買収により、日立は送配電分野で世界トップクラスのシェアを獲得しました。狙いは、再生可能エネルギーの普及で需要が拡大する送配電市場の獲得と、ABBが持つグローバルな顧客基盤や技術力の取り込みです。 この買収は、ABBの優れたハードウェア・制御技術(OT)に、日立のデジタルプラットフォーム「Lumada」(IT)を組み合わせることで、送配電網の効率運用や予兆保全といった高度なエネルギーソリューションの提供を可能にしました。これは日立が掲げる「OT×IT×プロダクト」戦略を具現化するものであり、現在「日立エナジー」としてグループのグローバル成長を牽引する重要な柱となっています。
海外企業の大型買収(2):GlobalLogic社の取得とDX事業の加速
エネルギー分野に続き、2021年には米国のデジタルエンジニアリング企業GlobalLogic社を約1兆円で買収しました。同社は、デザイン思考に基づくソフトウェア開発やデジタル体験の創出に強みを持つ企業です。この買収の最大の目的は、日立のLumada事業のグローバル展開を加速し、特に欧米市場でのDX(デジタルトランスフォーメーション)需要を取り込むためのソフトウェア開発能力を抜本的に強化することにありました。 GlobalLogicの獲得により、日立は世界各地のデザインスタジオやエンジニアリング拠点を手に入れ、顧客体験(UX)を重視したサービス開発力を強化しました。GlobalLogicが持つ「チップからクラウドまで」の幅広い技術力と、日立の産業・インフラの知見を融合させることで、多様な産業分野においてDXをワンストップで支援する体制を構築。この買収は、日立が伝統的な製造業からデジタルで成長するテクノロジー企業へと変貌を遂げるための決定的な一手となりました。
事業再編がもたらした経営・財務へのインパクト
財務体質の改善と収益性の向上を示す経営指標の変化
一連の事業再編により、日立の財務体質と収益性は劇的に改善しました。2009年3月期の巨額赤字からV字回復を遂げ、近年は安定して高い利益率を確保しています。
- 収益性の向上: 不採算事業の整理と高収益事業へのシフトにより、調整後営業利益(EBITA)などが大幅に改善。
- 資本効率の改善: 投下資本利益率(ROIC)を重要指標とし、資本コストを上回るリターンを安定的に創出。
- キャッシュフロー創出力の強化: 本業の収益力向上と事業売却により、成長投資や株主還元の原資となる営業キャッシュフローが潤沢になった。
- 財務の健全化: 大型買収を進めながらも、有利子負債は適切な水準にコントロールされている。
かつての低収益体質から脱却し、現在ではグローバルな競合他社と比較しても遜色のない、高い収益性を誇る企業へと変貌しています。
高収益事業へのシフトによる事業ポートフォリオの質の変化
事業ポートフォリオの質も大きく変化しました。ハードウェアの売り切り型ビジネスが中心で景気変動の影響を受けやすかった以前の構造から、収益が安定しやすいリカーリングビジネス(継続課金型ビジネス)の比率を高めました。Lumadaを中心としたデジタルソリューションや、インフラの運用・保守サービスなどがその代表例であり、利益率の向上に大きく貢献しています。 事業構成も、従来の重厚長大産業への依存から脱却し、現在は以下の3セクターを成長の柱としています。
- デジタルシステム&サービス: Lumadaを中核とするITサービス事業
- グリーンエナジー&モビリティ: エネルギー、鉄道など脱炭素化に貢献する事業
- コネクティブインダストリーズ: 産業・流通・水などの分野をデジタルでつなぐ事業
これらの分野は、DXや脱炭素といった世界的なメガトレンドと合致しており、将来の成長性が高い領域です。低成長・低収益事業から高成長・高収益事業へリソースをシフトさせたことで、企業全体の「稼ぐ力」が根本的に強化されました。
グローバル市場における競争力と企業価値の向上
事業再編と戦略的買収を経て、日立のグローバル市場における存在感は飛躍的に高まりました。現在、海外売上収益比率は6割を超え、名実ともにグローバル企業となっています。特に鉄道システムやパワーグリッド事業では世界トップクラスのシェアを誇り、欧米の主要プレイヤーと互角以上に競争できる体制を築きました。また、GlobalLogicの買収は、北米を中心とする巨大なデジタル市場へのアクセスを強化し、日本市場の縮小リスクを乗り越えて世界の成長を取り込む基盤となっています。 こうした変革は株式市場からも高く評価されています。事業の選択と集中によってシナジーが明確になり、かつて課題であった「コングロマリット・ディスカウント」は解消に向かっています。株価は上昇基調を維持して時価総額も大きく拡大しており、日本の伝統的大企業が構造改革を成し遂げた成功事例として、投資家から注目されています。
事業ポートフォリオ改革に伴う人材の再配置と組織文化の変革
大規模な事業の入れ替えは、人材の流動化と組織文化の変革を促進しました。事業売却に伴い多くの従業員がグループを離れた一方、ABBやGlobalLogicなどの買収を通じて、多様な国籍や専門性を持つ人材が数多く加わりました。特にGlobalLogicの統合は、シリコンバレー流のアジャイルな開発手法やスピード感あふれる文化を日立にもたらす契機となっています。 さらに、年功序列的な雇用慣行から、職務と成果に基づいて評価・登用する「ジョブ型」雇用への転換を推進。これにより、国籍や年齢に関わらず、適材適所の人材配置が可能になり、28万人を超える多様な従業員が「One Hitachi」として一体感を持ち、自律的に行動する組織風土への変革が進んでいます。
再編後の日立が描く未来図と向き合うべき課題
データとテクノロジーで持続可能な社会へ貢献するビジョン
大規模な構造改革を終えた日立は、「データとテクノロジーでサステナブルな社会を実現して人々の幸せを支える」というビジョンを掲げています。今後の成長ドライバーとして、グリーン(脱炭素)、デジタル、イノベーションの3つを軸に、社会イノベーション事業を通じて地球環境の保全と人々のウェルビーイングの両立を目指します。 中核となるLumadaは、生成AIなどの最新技術を取り込みながら、顧客の現場データ(OT)と経営データ(IT)を融合させ、社会インフラの自律運用や経営の全体最適化を支援するプラットフォームへと進化させていく方針です。エネルギー、モビリティ、インダストリーといった分野で社会課題を解決することで経済的価値を生み出し、それを再投資してさらなるイノベーションを創出する好循環の実現を目指しています。
買収事業とのシナジー創出:PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)の重要性
今後の成長にとって、巨額を投じて買収したABBパワーグリッド事業(現日立エナジー)やGlobalLogic社とのシナジーを最大化することが最重要課題です。買収後の組織統合プロセスであるPMI(Post Merger Integration)の成否が、投資の成果を左右します。特に、ハードウェア中心の文化を持つ日立と、ソフトウェア中心でアジャイルな文化を持つGlobalLogicとでは、働き方や意思決定のスピードが異なります。これらの文化を融合させ、互いの強みを引き出す体制を構築できるかが鍵となります。 具体的には、GlobalLogicのデジタル技術を日立のインフラ事業に適用してサービス化を加速させたり、日立エナジーのグローバルな顧客基盤にLumadaのソリューションを販売(クロスセル)したりといった戦略が期待されます。人材交流や共同プロジェクトを通じて連携を深め、買収価格に見合う、あるいはそれ以上の価値を創出できるかが問われています。
残存する非コア事業の整理と今後のポートフォリオ戦略
主要な事業再編は一巡しましたが、日立のポートフォリオ改革に終わりはありません。経営陣は「不断のポートフォリオ見直し」を掲げており、今後も環境変化に対応して事業の入れ替えを継続する方針です。これからは、かつてのような大規模な売却ではなく、各事業セクター内での中小規模の事業の選別やカーブアウト(事業切り出し)が中心になると考えられます。 同時に、新たな成長領域への投資も継続されます。特に、生成AI、量子コンピュータ、グリーン関連ビジネスといった先端技術分野では、自前主義にこだわらず、スタートアップとの連携やM&Aを柔軟に活用していくでしょう。常に最適な事業構成を追求し、変化し続けることで、持続的な成長と企業価値の向上を目指す日立の変革は、今もなお進行形です。
まとめ:日立の事業再編から学ぶ、持続的成長への戦略
本記事では、日立製作所が未曾有の経営危機を乗り越え、グローバルな高収益企業へと変貌を遂げた事業再編の軌跡を多角的に解説しました。その核心は、社会イノベーション事業を中核に据え、デジタル基盤「Lumada」を羅針盤として「選択と集中」を徹底した点にあります。非コア事業の売却で得た資金を、ABBパワーグリッド事業やGlobalLogic社の買収といった成長領域へ大胆に再投資することで、事業ポートフォリオの質的転換を加速させました。この一連の改革は、財務体質の改善のみならず、ハードウェア中心のコングロマリットからデータとテクノロジーを駆使するグローバルソリューション企業への変革を成し遂げ、企業価値を大きく向上させています。日立の事例は、明確なビジョンに基づき、痛みを伴う改革を断行することの重要性を示しており、自社の事業ポートフォリオ見直しや経営戦略を検討する上で、極めて示唆に富むものと言えるでしょう。